社会問題の構造にメスを入れるメディアを。リディラバジャーナル5周年インタビュー(前編)

社会問題の構造にメスを入れるメディアを。リディラバジャーナル5周年インタビュー(前編)
2023年に5周年を迎えた、社会問題を構造化するメディア「リディラバジャーナル」。
今回は編集長の安部に、5年間の軌跡や構造化というコンセプトにこだわり続けてきた理由を聞きました。
前編では、「あるのは思いだけ」という状況から事業を立ち上げた経緯や、当時感じていたメディアの課題などを振り返ります。
聞き手は、リディラバ ジャーナル編集部の井上です。
※本記事は23年6月6日に開催した「【リディラバジャーナル5周年/編集長インタビュー】赤字でも構造化をやりぬく。編集長・安部敏樹が語る『社会課題メディア』の未来」を編集してお届けしています。
「現場に行く」だけでは伝えられないことがあった
メディア立ち上げのきっかけ
井上
リディラバジャーナルは、社会問題を多面的かつ構造的に捉えられる記事をお届けするべく運営しています。そもそも、なぜ社会問題に特化したメディアを立ち上げようと思ったのでしょうか。
安部
まず、リディラバは設立当初から一貫してスタディツアーを展開してきました。
参加者は社会問題の解決を目指す現場に足を運び、問題の当事者や解決のトップランナーと直接関わりながら、自分にできるアクションを考えるというものです。

当初、仲間たちと議論しながらツアーの内容をブラッシュアップして、種類もどんどん増やしていきましたが、あるときから「ちょっとまずいかも」と感じる状況が出てきて。
井上
どんな状況ですか?
安部
ツアーを受け入れてくれる現場は、革新的で独自の試みをしているトップランナーが多い。
参加者たちは、優れた解決のアプローチに感銘を受け、「すばらしい」と感動して帰ってくれる。でも、その解決事例がすべての現場でそのまま適用できるわけではない。
ツアーだけでは、「なぜ問題が発生しているのか」という全体像を把握しきれないこともあると感じたんです。
また、ツアーで足を運べる範囲には限界もあります。たとえば児童養護施設では、個人のプライバシーの観点から、実際に子どもたちと会うことはできません。
ツアーだけでは伝わりにくい問題の構造や、体験できない現場の実態を伝える手段が必要だと感じ、社会問題に特化したメディアを立ち上げようと思いました。
「みなさん考えましょう」で終わっていいのか
問題の構造を伝える必要性
井上
既存のメディアでは、その機能は果たせなかったんでしょうか。
安部
そうですね。当時、「なぜメディアはニュースの背景にある問題の構造にメスを入れないのか」と思っていました。
たとえば、保護者が子どもを虐待したというニュースが、何件か続けて繰り返し流れる。同じことが起きないよう何らかの手立てを講じる必要があるのに、「みなさん考えましょう」という言葉で終わってしまう。
メディアは調査や情報収集をする中で、現場で渦中にいる人よりも全体像が見えるはずです。持っている情報量で言えば、理論上はその問題の構造のボトルネックも特定できる。それなのに、していないと。
虐待が起こるたびに、考えるよう促すことはもちろん無意味だとは思いませんが、問題の構造に向き合い、解決に貢献できるような当事者意識や責任感を持ったメディアが必要だと感じました。

あと、NPOなど現場の方々にお話を聞くと、既存メディアへの不信感を抱えていることが多くて。「もうメディアにあまり情報を出したくない」という声ももらいました。
すでに大手メディアに取り上げられている団体もいましたが、取材に来たディレクターから「台本通りに喋ってください」と言われたこともあったと。
それでは現場の実態とかけ離れてしまうけれど、台本と違うことを話したら放送してもらえない。取材に来るのも結局一度きりで、その後、特に関わることもなかったそうです。
既存メディアへの不信感もある中で、ツアーで現場と継続的な関係を築いてきたリディラバ だからこそできる、メディアの作り方があるのではないかと考えていました。
意見が異なる人にも話を聞きに行く
メディア運営で大切にしていること
井上
ある種の使命感を持って始まったリディラバジャーナルですが、立ち上げ時はかなりハラハラしたそうですね。
安部
そうですね。立ち上げ時には内外で反対の声もありました。
当時、経営面や各事業の進捗度合いを見ても、メディアを立ち上げる準備が整っているとは言えませんでした。
某幹部からは「安部くん、知ってる?メディアは本当に儲からないから大変だよ」と、極めて洗練された忠告をいただいたこともあります。
井上
妥当な指摘ですね(笑)。
安部
5年間やってみて、それが妥当な指摘だったことは、ひしひしと感じてますね(笑)。
井上
リディラバジャーナルも5周年を迎えましたが、メディアを運営する上で大切にしてきたことを教えてください。
安部
一つは、自分とは異なる意見や、自分が理解できない主張をしている人にも直接話を聞きに行くことです。
井上
「ヘイトスピーチ」特集では「在日特権を許さない市民の会」(以下、在特会)の八木会長に、「痴漢大国ニッポン」特集では30年間痴漢をしていたという男性に、そして「難民問題」特集では、いわゆるヘイト本の「そうだ、難民しよう」の著者・はすみとしこさんをオフィスに招いて取材しました。

(在特会の八木会長。「ひどいことをしたなと思いますが…在特会会長の告白」より)

(自らの痴漢加害について語る男性。「痴漢し続けて30年…元加害者の告白」より)

(『そうだ難民しよう!』の著者、はすみとしこさん。「『そうだ難民しよう!』が支持される日本社会」より)
安部
お互いに意見が異なっていたとしても、僕ら側が話してもらえる人間であるべきだと思っています。
もし、在特会の八木会長に、会っていきなりバーンと机をたたいて「あんなヘイトスピーチをするなんて、何を考えてるんだ」と言いそうな人間だと思われていたら、そもそも八木会長は話をする場を持ってくれなかったと思います。
彼には彼の主張があり、当然、相手も僕が異なる意見を持っていることは理解していたでしょう。それでも「ちょっと自分の思いを話してみようかな」と考えてくれた。
そうした絶妙な距離感や信頼関係を、薄氷を踏むように慎重に作っていくことが、取材を進める中でとても大事なことだと思いますね。
加害が繰り返されないように、加害の要因を明らかにする
安部
もう一点、なぜ加害者とされる立場の方への取材をするかというと、加害の要因を明らかにすることが次の被害者を生まないために大事だと思っているからです。
もちろん、大前提として、まず被害者の立場に立って被害者を擁護すべきです。被害者本人やその家族が強く擁護を求めたり、加害者に怒りを覚えて厳罰を求めたりするのは、当然のことだと思います。
一方で、ネット世論を見ていて思うのは、全く関係のない第三者が感情的に加害者を罰したがる傾向があることです。これについては課題を感じています。
被害者に全力で寄り添うことが基本ですが、第三者である以上は、直接的に介入して解決できることは限られます。
日本では、逮捕され有罪が確定すれば、司法に基づいて罰せられる。加害者にはそのプロセスでまず罪を償ってもらいたいですが、それとは別に「なぜ罪を犯してしまったのか」ということは、私たちもきちんと理解しておく必要があります。
次の加害・被害が繰り返されないために、社会は何をすべきか。その方向性を提示するために、加害の背景にある要因やメカニズムを構造的に伝える。それが私たちが第三者として社会問題に関わるときのスタンスです。
中編「課題解決を加速させるために“構造化”する——。リディラバジャーナル5周年インタビュー」に続きます。



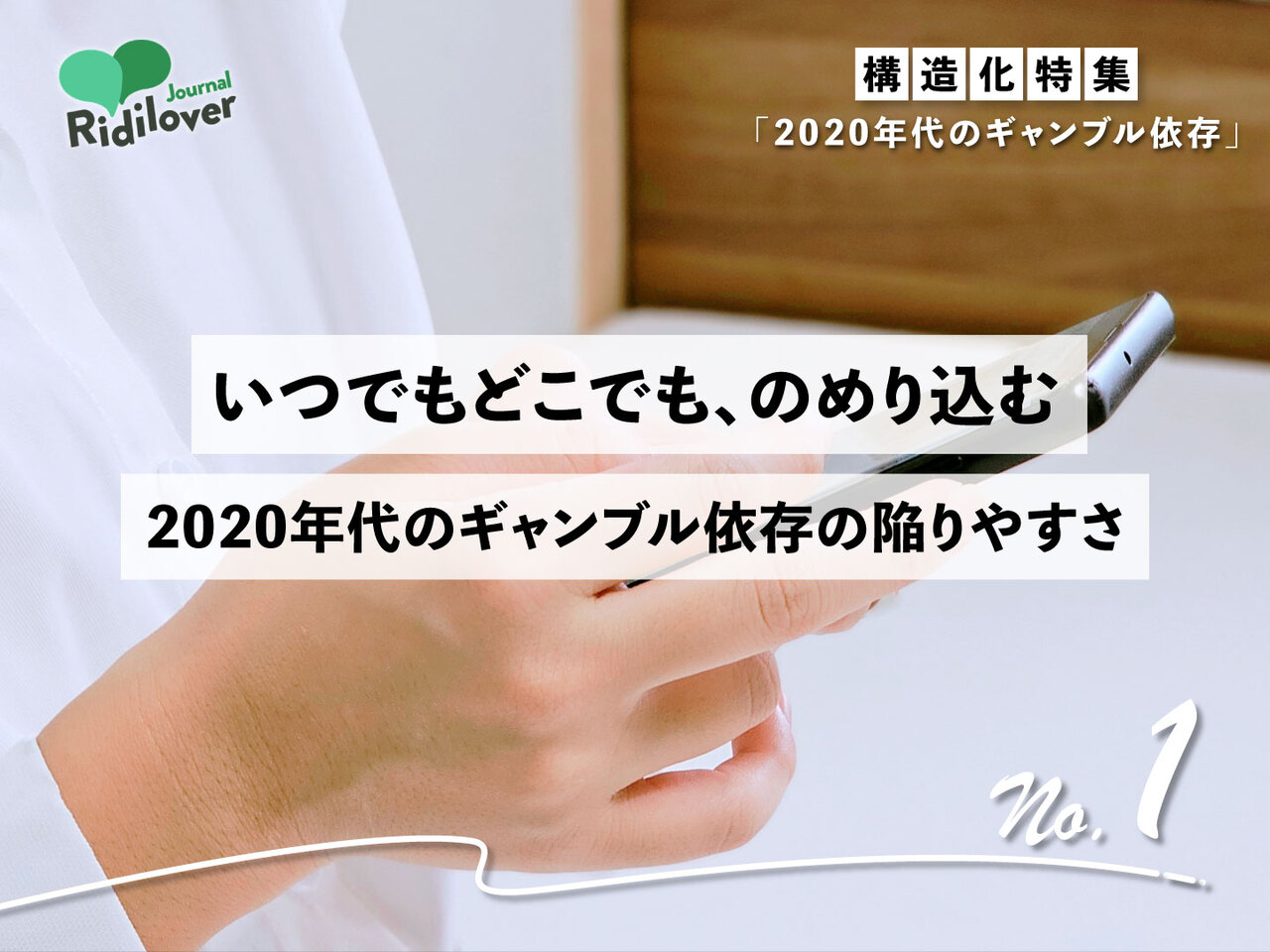




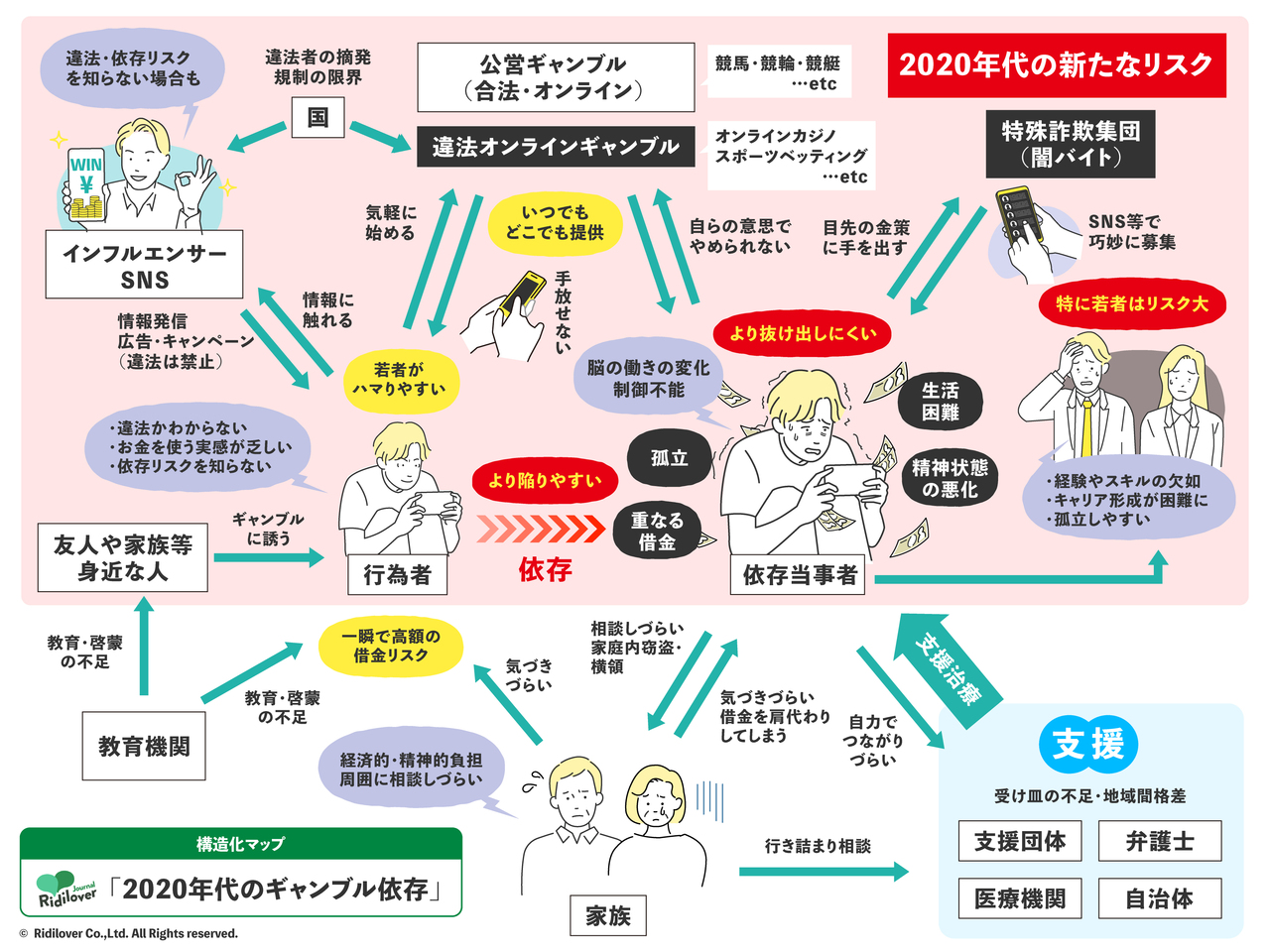






こんにちは。リディラバジャーナルです。「社会貢献したい。だけど具体的に何をしたら良いかわからない」「社会課題へ関心を持ち続けたいけど、SNSで言い争っている人たちがいたから、見なかったことにした」そんなモヤモヤを抱える大学生のみなさんへ、持続可能な社会課題との向き合い方のヒントとなる記事をお届けします。
※このページからリディラバジャーナルの記事にアクセスすると、どなたでも3月3日(火)まで無料でお読みいただけます!
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる