親も子も、ここにいてもいいんだと思える社会へ 「メシが食える大人」を育てる学習塾が、野外体験に取り組むワケ

親も子も、ここにいてもいいんだと思える社会へ 「メシが食える大人」を育てる学習塾が、野外体験に取り組むワケ
全国に195か所360教室を展開する花まる学習会代表の高濱正伸さんが、思考力・国語力・野外体験を3つの柱とした塾を立ち上げたのは、30年前。バカンスでもなく、ツアーでもない、「生きる力」を育むスクールとして、毎年延べ10000人の子どもたちを引率し続けている。
子どもにとって必要な力とそれを育む「体験」とはどんなものなのか。
子どもの問題を考えていく上で、子育てを社会でどのように支えていくべきなのか。
花まる学習会の実践を通して、高濱さんが考え続けてきたその思いを聞いた。
【高濱正伸】
花まる学習会代表
1959年熊本県生まれ。東京大学卒、同大学院修了。1993年、「メシが食える大人に育てる」という理念で「花まる学習会」を設立。NPO法人子育て応援隊むぎぐみ理事長、算数オリンピック委員会作問委員、日本棋院理事。保護者向けの子育て講演会のほか、『伸び続ける子が育つお母さんの習慣』など著書多数。2020年から無人島プロジェクトを開始。
目指したのは「メシが食える大人」を
育てるための学習塾
――高濱さんが代表を務める花まる学習会では、思考力・国語力・野外体験を3つの柱にされていて、一般的な学習塾とは一線を画しているように思うのですが、どんなきっかけで立ち上げられたのですか?
花まる学習会を始めたのは1993年です。当時、予備校講師としての仕事で十分に生計を立てることができていたんですけど、あるとき、中堅クラスへ授業に行ったら40〜50人ぐらいのクラスの大多数の生徒に、いわゆる「ひきこもり」傾向があったんです。日本で「ニート」という言葉が使われるようになるよりも前の話です。
調べてみると、本当に相当な数の「社会的ひきこもり」状態の子どもがいることがわかってきました。当時は子どもが学校に行かなくなっても、学校教育の現場では誰が責任をとるわけでもなかったんです。「教育現場で、根本的に何か間違ったことが進行しているな」と感じました。
それで、学校に入って革命を起こすみたいなことも考えたんだけど、私が出した答えは、子どもたちを「メシが食える大人」に育て上げるための塾を始めることでした。
――「メシが食える大人」に育てる学習塾とは、まったく新しい試みだったかと思いますが、最初からビジョンが見えていたんですか?
思考力・国語力・野外活動という三本柱は当初から明確に見えていました。
それまで予備校講師として出会った生徒の中には、心がネガティブになっていて「どうせ俺なんかダメだ」というふうに、コンプレックスで凝り固まっている子がいたんですね。そういう生徒をみると、これは「心」の問題だなと。そこから「思考力」というキーワードが出てきました。
そして、思考力のためには「国語力」が大事だと考えました。言葉の力をつけないと、考えられないからです。
さらに、考えるための脳が何をもって伸びるかというと、「体験」です。没頭して大好きなことを繰り返す体験をすると創造性や集中力などの脳の力が伸びるんです。
脳の力を伸ばすということを考えた時に、幼児から大学院生まで全学年を教えてみて、小学校5年生以降になると難しいと感じるようになりました。思春期に入ってくると、コンプレックスが強くて呪いが解けないような状態になってしまう。5年生くらいまでに「ここにいてもいいんだ」と思える感覚とか、遊び込んだらもう止まらない感じとか、そういう体験をすることが大事だということがわかってきました。

(写真:川の中から見た、子どもが水中ゴーグルをつけて水中探索をする様子)
脳の力を伸ばす「質の高い体験」とは
――子どもの脳の力を伸ばす「質の高い体験」というものがあるとしたら、高濱さんはどんなものだと思われますか?
脳の力を伸ばすのに1番いいのは、何にもない野原で子どもたち同士で「あそこに基地をつくろう」とか、川で「ダムをつくってみよう」とか、そんなことをひたすら繰り返すような体験です。あと、無人島で遊ぶとかね。禁止事項ばかりの公園と違って、無人島は制限が少なくていいですよ。
本当は、危ないことを自分たちで制御しながら遊び抜くみたいな場面で子どもたちの最高の集中力が出るんだけども、日常ではそういう場がなかなか確保できません。ならば自分が連れて行くしかないと、花まる学習会を始めたのが30年前。今、そのときの決断はまったく間違っていなかったという手応えがあります。

(写真:川の外から見た、子どもたちが川面に顔をつけて観察する様子)
――脳の力を伸ばすのに、小学校5年生が一つの境目になるというお話がありましたが、中には、環境などに恵まれずに、結果として中高生や大学生になったときに、自己肯定感を持てていなかったり、対人コミュニケーションなどの課題が表面化して不登校になったりしてしまう子もいるかと思います。
10歳以降であっても、大きく変われた人もたくさんいます。実は私自身もそうで、自信のなさを高校生くらいまで引きずっていました。
10歳以降は、メンターといえるような人との出会いがカギになります。「この人についていこう」と惚れ込めるような人との相互作用のあるコミュニケーションを通して成功体験を積んでいくと、自信を持てるようになってきます。
――花まる学習会は年間1万人の子どもたちに体験を届けていて、本当にすごいことだなと思うのですが、課題はありますか?
ずっと課題だと思っていたのは、金銭的に余裕のある家庭の子どもしか参加できないということです。無料枠をつくったこともありましたが、「あの子は無料枠で来ているんだよ」という差別が起こり得るので、親も申し込みをためらうんですね。
子どもたちに体験を与えるべきだし、それを通して成功体験を掴めると、子どもたちの人生にどんどんプラスに作用していきます。だから、都会では失われてしまった外遊びを、すべての子たちにやらせてあげたいと、ずっと思っていました。
人のネットワークの網目の中に
自分がいるという感覚を親が持てるか
――子どもが学校へ行かなくなっても、学校教育の現場では誰も責任を負わないというお話がありましたが、子どもの教育に関して最終的な責任を誰が負うのかという話になった時に、多くの人が思い浮かべるのは親なのではないかと思います。ただ、親の自己責任論で片付けるには無理があるようにも思えます。
私はこれまでに数えきれないくらい講演をしてきましたが、保護者に対して「正しい子育てはこうなのに、あなたはできていない」みたいな話を論理的にしても意味がないんです。
最初は、「なんでこんなことも分からないのか」と疑問に思っていました。しかし、「正しい子育て」を孤立したお母さんに押しつけている自分の方が間違っていたんだと、あるときに気付いたんです。
というのも、そもそも人類は何万年の歴史の中で子育てを「群れ」でやってきたのに、この70〜80年はお母さんと子どもという単位になってしまった。
つまり、本来は1人の母さんと赤ちゃんがいたら、身近に2〜3人は子育てを経験しているおばちゃんおじちゃんがいて「かわいいね、あなたの小さい時によく似てるね」なんて言いながら、お母さんが疲れていれば「私が代わりに抱っこしてるから、少し寝てきたら?」とか「あなたよく頑張ってる。私たちのときよりよっぽどいいよ」というように、思いやりとねぎらいとあたたかさの中で子育ては成立していたんです。それが今は壊れてしまっているっていうことに私が気づいたのが、25年ぐらい前ですね。
お母さんが子育てでイライラしたり不安になったりしたときに、側にいて「大丈夫だよ、あなたはよく頑張ってるよ」と言い続ける人がいるっていう状況を作っておかないと子育ては無理なんです。つまり、「正しい子育て方法があって、それを親がちゃんとやる」っていう思考が、そもそも間違っている。子どもの問題は、家庭だけに介入しても解決しません。
大事なのは、子どもの自己肯定感で、現代社会におけるその最大関数は母親の自己肯定感です。お母さんの安定が1番。普段、ともに長い時間を過ごす母子は直接的に影響し合っているから、お母さんが壊れると、子どもはどんどん不安になる。
お母さんの心の安定を支えるためには、お母さん自身が人のネットワークの網目の中に自分がいるという感覚を持てることが大切です。だから、親が社会的に孤立せずに、精神的に安定して子育てができる社会をつくっていくことが第二の仕事だと思いました。

(写真:高濱正伸さん)
―――仮に無料の体験があったとしても、親が行かせようと思わないと子どもは参加できません。そもそも、親が孤立していたら、無料の体験の機会があるということすら知らないということもあります。
花まる学習会で無料枠をつくったときは、本当に届けたい子どもへ体験を贈ることはなかなか難しかったのですが、リディラバさんとの子どもの体験格差解消プロジェクトでは、日常的に困難家庭の子どもの支援をしたり、あるいは日常的な保護者支援をしたりしているNPOの団体と連携しているのがいいですね。そこを経由して子どもたちに募集をかけるという形なので、応募する側も参加しやすいはずです。
自然の中の危険に満ちている感じとか、心の底から楽しいという感覚とかを味わって育った人は胆力がある。器が大きいと言い換えてもいい。
それはこの30年の経験から確かに言えることで、すべての子どもたちに体験を届けたいというのは、ずっと思い続けてきたことでもあります。このプロジェクトが「体験をすべての子どもたちに与えよう」という合意形成の一歩目になるといいと思っています。

(子どもの体験格差解消プロジェクト 詳細はこちら)






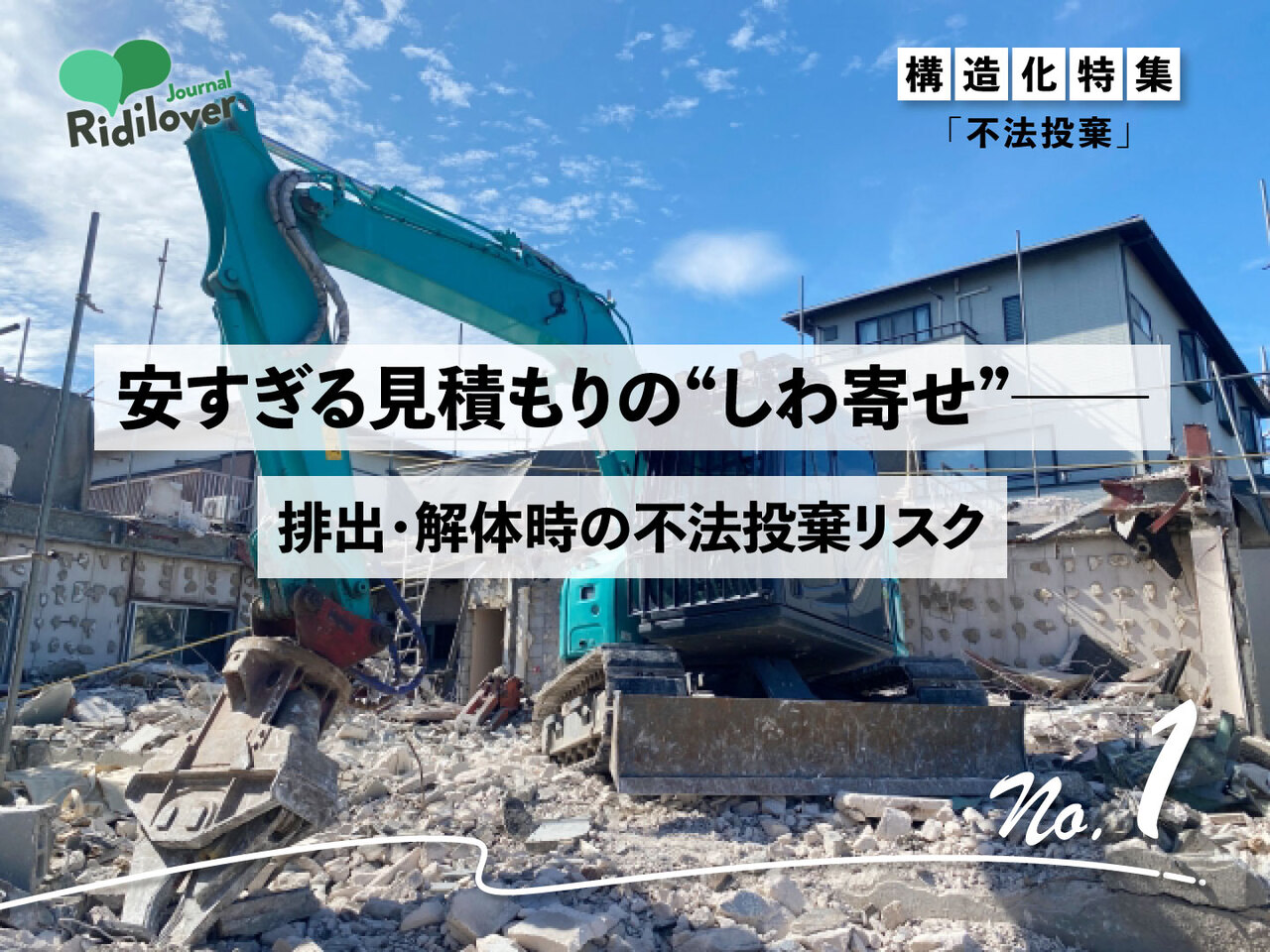







ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる