
生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育て
生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度がある。児童虐待や不妊など、様々な事象の結節点ともなる「特別養子縁組」。本特集では、公的機関と民間事業者の取組みの違いや、児童相談所の業務体制など制度を取り巻く構造を紐解く。

生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度がある。児童虐待や不妊など、様々な事象の結節点ともなる「特別養子縁組」。本特集では、公的機関と民間事業者の取組みの違いや、児童相談所の業務体制など制度を取り巻く構造を紐解く。
生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度がある。児童虐待や不妊など、様々な事象の結節点ともなる「特別養子縁組」。本特集では、公的機関と民間事業者の取組みの違いや、児童相談所の業務体制など制度を取り巻く構造を紐解く。

「児童相談所に言いづらいこともいっぱいあるわけですよ」
東京都児童相談センター(中央児童相談所)の相談援助課長・上川光治さんはそう言って、特別養子縁組をする生みの親や、養親(養子を家族として迎える親)の心情を慮ります。

東京都児童相談センターにて特別養子縁組の担当をする児童福祉司・諏訪明子さん(左)と相談援助課長の上川光治さん(右)。
児童福祉法の改正によって、2017年4月から養子縁組支援が児童相談所の業務として明確に位置付けられ、児童相談所では生みの親や養親の相談受付も担うことになっています。
ですが、児童相談所は相談を受付ける機関であると同時に、虐待などから子どもを保護する場合には親子関係を分離する機関でもあるのです。
そのため、生みの親や養親は児童相談所に子育て相談をして「養育ができない親だ」と思われることを危惧することがあります。つまり、児童相談所が「相談しにくい場所」になってしまっているのです。
...
































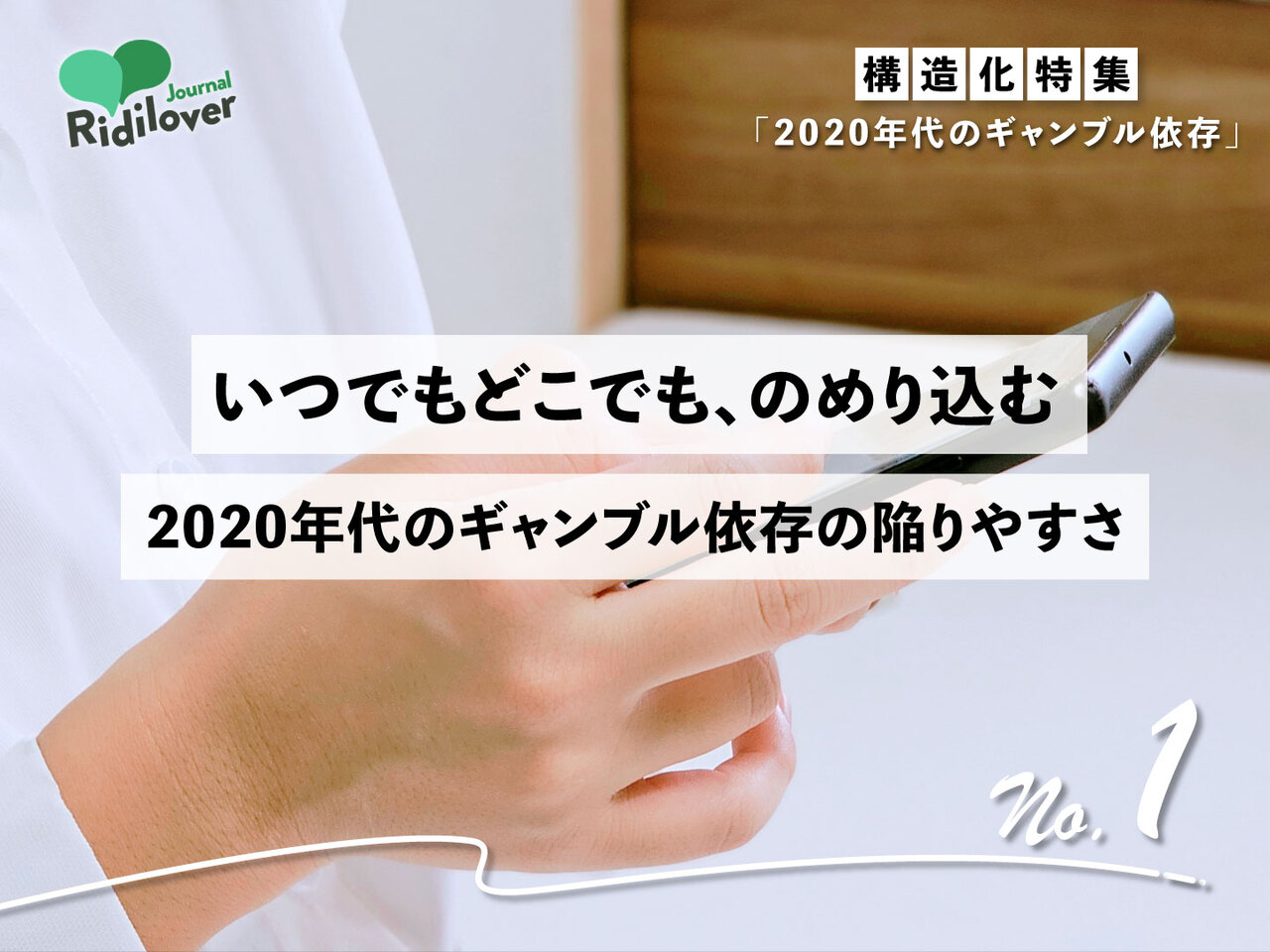




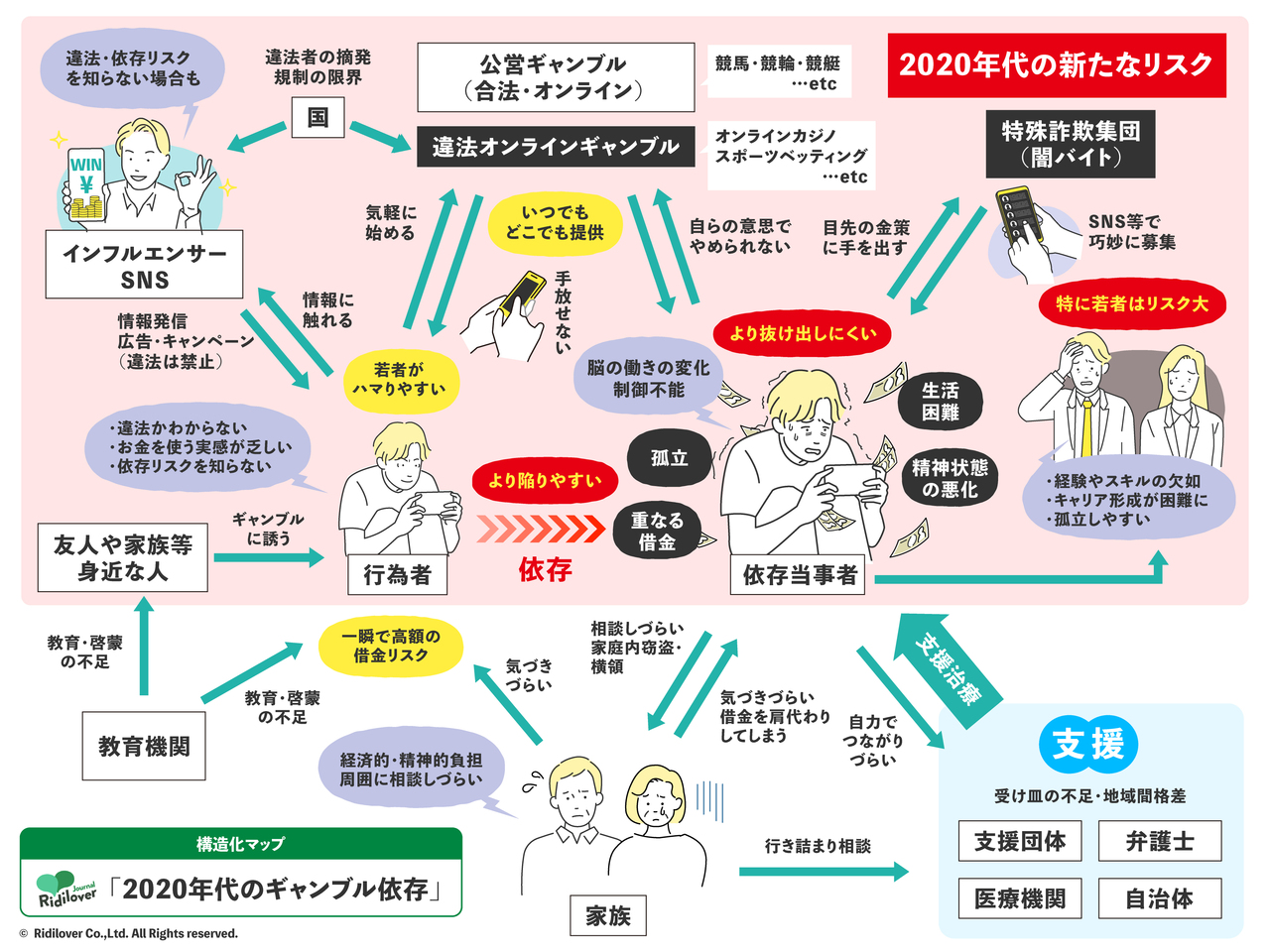






こんにちは。リディラバジャーナルです。「社会貢献したい。だけど具体的に何をしたら良いかわからない」「社会課題へ関心を持ち続けたいけど、SNSで言い争っている人たちがいたから、見なかったことにした」そんなモヤモヤを抱える大学生のみなさんへ、持続可能な社会課題との向き合い方のヒントとなる記事をお届けします。
※このページからリディラバジャーナルの記事にアクセスすると、どなたでも3月3日(火)まで無料でお読みいただけます!
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる