未来へのシカケ/Case2. 地域支援「コミュニティナース」(後編)

未来へのシカケ/Case2. 地域支援「コミュニティナース」(後編)
リディラバジャーナル新連載「未来へのシカケ」。
この連載では、社会課題への深い洞察に基づく、課題解決に向けた取り組みを紹介する。
第2回となる今回のテーマは、予防医療を軸にした地域支援。
前編では、Community Nurse Company株式会社の創業の経緯と目指す世界観などを聞いた。
後編では、目標の実現に向けた各事業を紹介しながら、地域コミュニティのあり方を考察する。

矢田 明子(やた あきこ)Community Nurse Company株式会社 代表取締役/一般社団法人 Community Nurse Laboratory 代表理事。島根県出雲市出身。父の死をきっかけにコミュニティナース着想。2014年島根大学医学部看護学科卒業後、自身も活動しながらコミュニティナーシングの担い手の育成を開始。2017年Community Nurse Company株式会社を設立し、コミュニティナーシングの社会実装を本格化。島根県雲南市に拠点を構えながら、全国の企業や自治体と連携し、コミュニティナーシングの社会実装を進めている。著書「コミュニティナース ―まちを元気にする“おせっかい”焼きの看護師」。2022年第10回アジア太平洋高齢者ケア・イノベーションアワード HOME CARE FOR AGEING-IN-PLACE部門グランプリ受賞。
受益者だけでなく、その家族も元気にするビジネスモデル
人とつながりまちを元気にする「コミュニティナース」。
矢田さんは、日本全国にこの取り組みを広めるため、さまざまなビジネスモデルによる収益化を試みてきた。
そんな中、2020年のコロナ禍を機に始めたのが「ナスくる」だ。
従来、コミュニティナースは地域に入り込み、目の前の人を元気にすることを目的に活動してきた。
ところがコロナ禍で移動や外出が制限される中、矢田さんはコミュニティナースの新たな可能性に気づく。
「コロナ禍の初期に、『私の代わりに、親を訪問してもらうことはできますか』という内容の問い合わせが来て、私はハッとしました。
目の前の人を元気にすることは、本人にとってためになるだけではない。
物理的に目の前にいない、本人に関わる人にもよい影響を与えられるんだと気づいたんです。
コミュニティナースが高齢の親をサポートすることで、子どもも安心するはず。
ならば、親子どちらも元気にできるような仕組みを作ろうと思い立ち、生まれたのが『ナスくる』です」
高齢者の孤立はコロナ禍でも大きな課題となったが、内閣府が行った「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」によれば、他人と話さない日があると回答した高齢者が、全体の約10%に上っている。
一人暮らしの高齢者に限っては、その割合が約40%にまで上昇し、さらに約10%が1週間に1回も他人と話さないと回答している。
また、他人との会話頻度と主観的な健康状態の相関関係を示唆する調査もある。
内閣府の「平成30年版高齢社会白書」によれば、健康状態が「良い」人では、「ほとんど毎日」会話する人が90.1%に上る一方、健康状態が「良くない」人では67.2%にとどまる。
また、健康状態が「良い」人では、「ほとんど会話をしない」が1.1%と極めて低いのに対し、健康状態が「良くない」人では13.1%で、12ポイントの差が見られた。

矢田さんが「ナスくる」で掲げた「つながりとトキメキのある日常を一緒につくろう」というビジョンには、他人との接点が少ない高齢者たちにも積極的に関わろうとする姿勢がうかがえる。
「高齢者本人が、必ずしも『つながりが足りていない』と感じているわけではありません。
他の人に迷惑をかけずに、自分でがんばろうという気概で、あえて接点を持っていないこともありますから、接触頻度の低さだけを取り出して、良し悪しを判断することはできないでしょう。
とはいえデータから見れば、他人とのつながり状況が、高齢者の心身の健康に影響する可能性は高い。
本人とその周りの人たちを元気にできるのであれば、私たちが自らつながりを作りにいくことは大切だと思っています」
しかし、矢田さんたちの思いとは裏腹に、「ナスくる」事業は思わぬ壁に直面することになる。
子からサービス申し込みがあっても、受益者となる親に敬遠されてしまう例が後を断たなかったのだ。
「『ナスくる』は、いわば高齢者の見守りサービスの一種です。
都市部では、見守りがセキュリティや防犯と同等の文脈で認識され、高齢者のサービス受容も進みつつあります。
でも地方の高齢者にとっては、依然として心理的ハードルが高いまま。
『見守られている』ことを『他人に迷惑をかけている』と認知し、サービス導入を拒否する人も少なくありませんでした」
受益者に嫌がられないように、つながりを作るにはどうすればいいのか。
矢田さんたちが考えて出した答えが、ファミリークラウドファンディング、通称「ファミクラ」だ。

第三者の余剰の優しさが生む、共助のシステム
2023年4月にリリースされた「ファミクラ」は、親の夢や願いを応援するサービス。
ファーストコンタクトで親の心を掴むため、クラウドファンディングという形態を採用した。
「クラウドファンディングという言葉自体、ある程度認知が広まってきているので、話の取っ掛かりに使いやすいんです。
たとえ本人が知らなかったとしても、『あらやだ、まだご存じでいらっしゃらない!?』と、知ってて当たり前のものとして会話を進められますし(笑)。
しかもクラウドファンディングは、寄付というよりは『人から応援を募る公の仕組み』です。
見守られるのが嫌な人でも、応援されるのはやぶさかでないもの。
内容を説明すると、導入を前向きに検討してもらえることが増えました。
もちろん、本人の応援してもらいたいことが最初から明確になっているわけではありません。
でも、時間をかけて対話していけば、確実に何かしらの夢が出てきます。
それをしっかりと拾い上げて、他の人たちに応援してもらう仕組みを作るのが、私たちの役割です」
「ファミクラ」の特徴は、完全クローズド型のクラウドファンディングであるという点だ。





































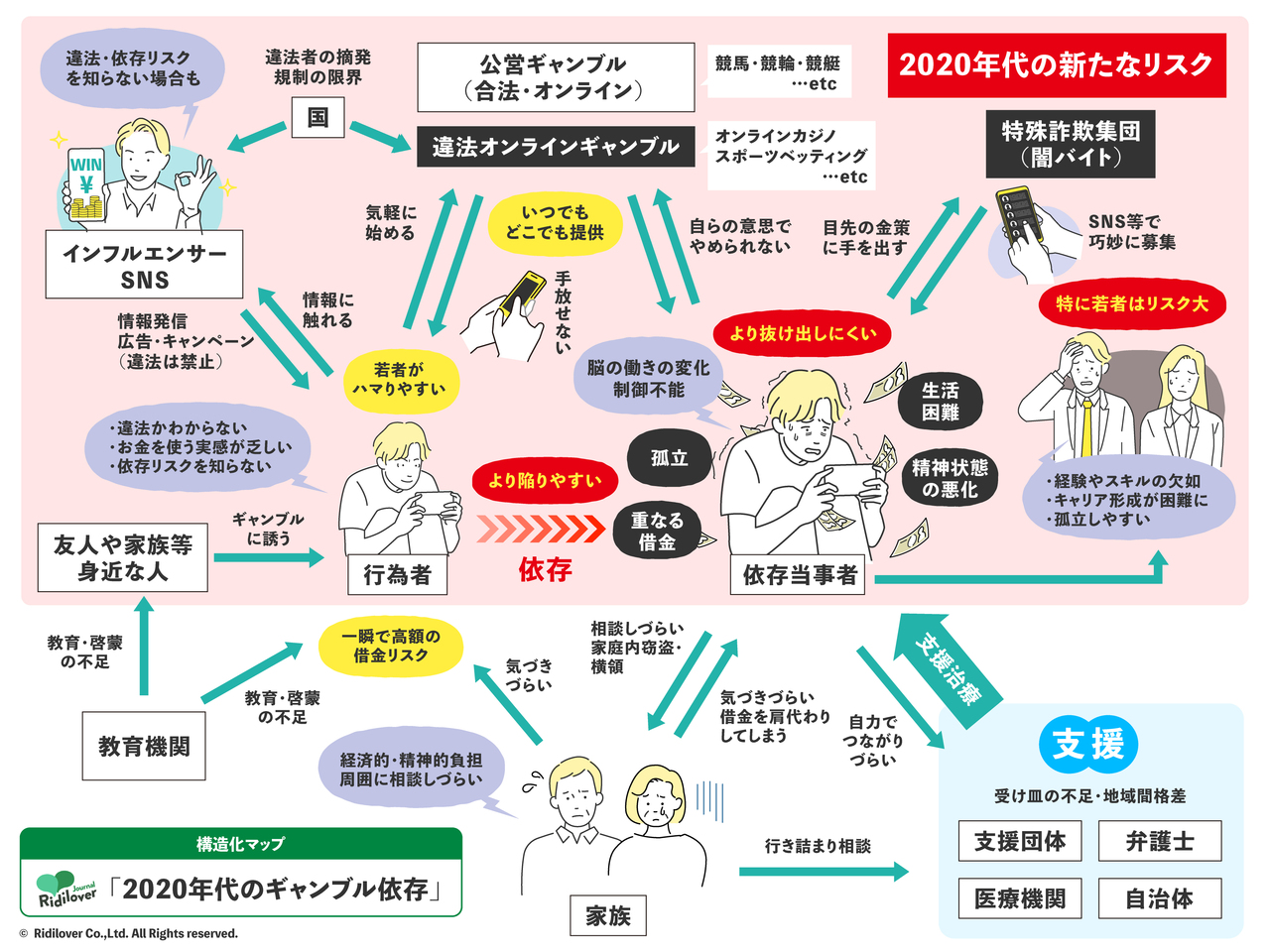






ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる