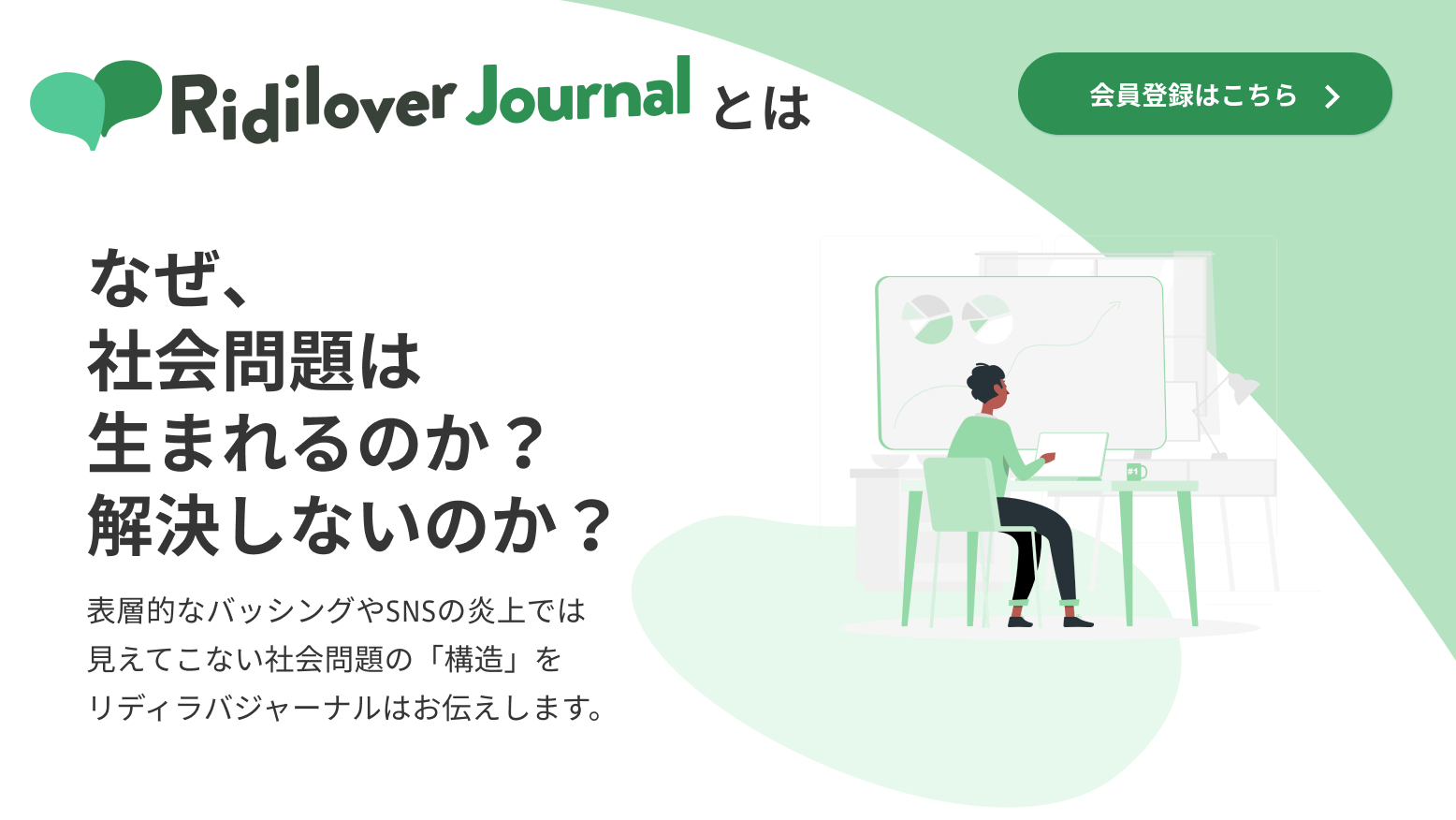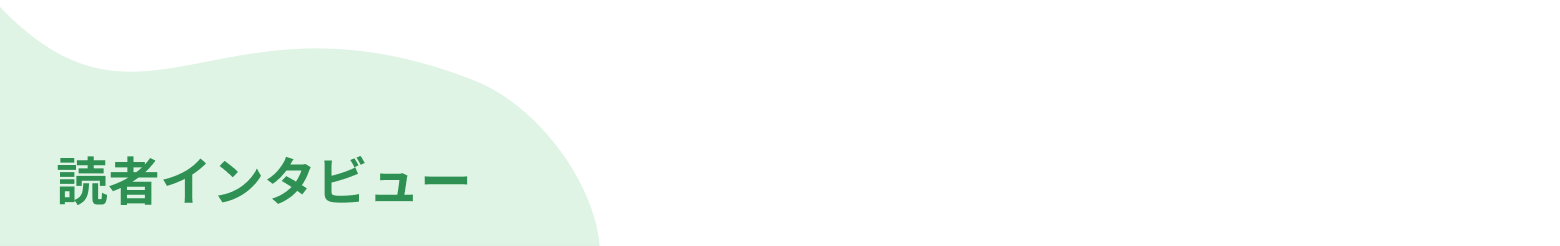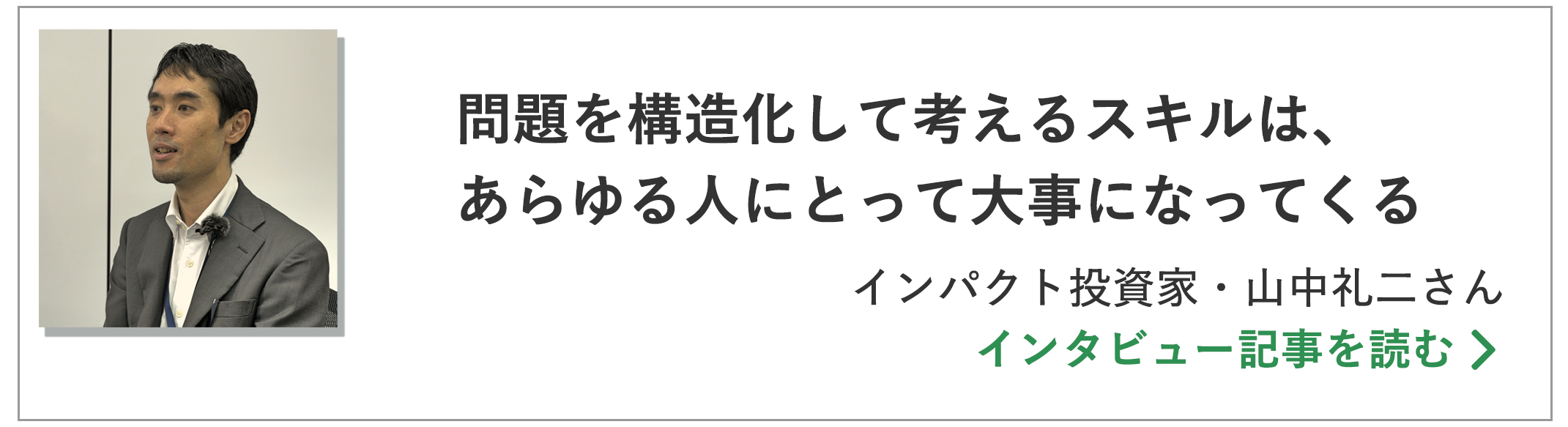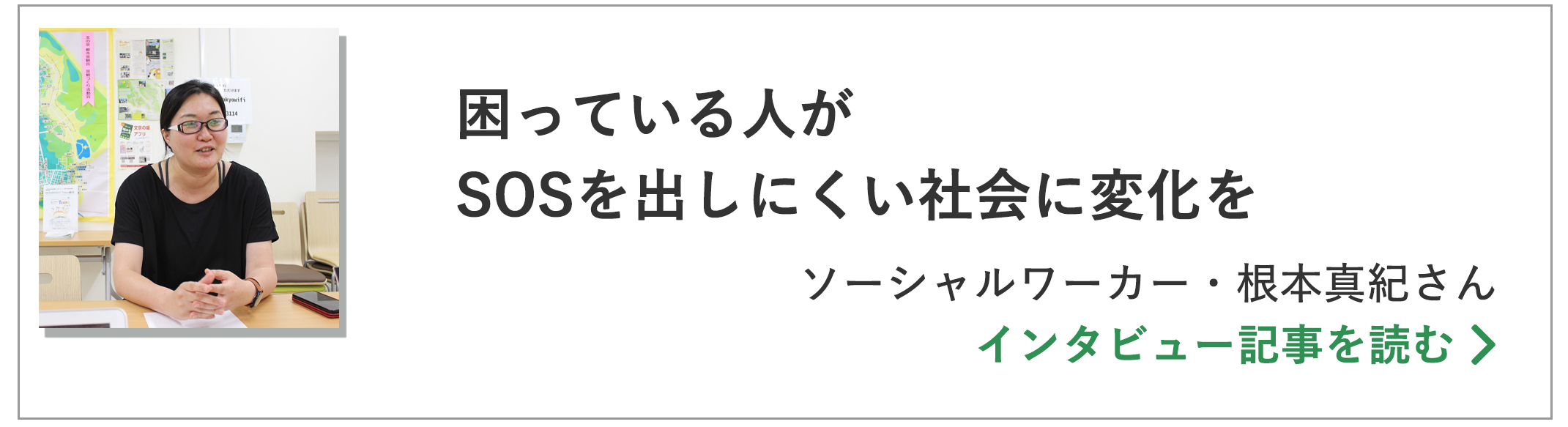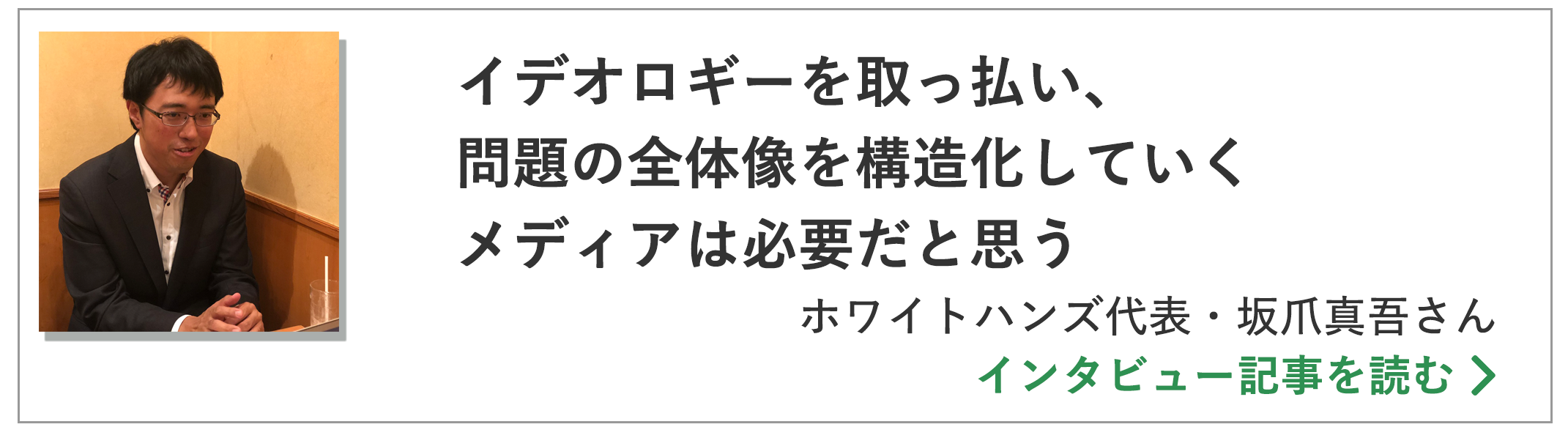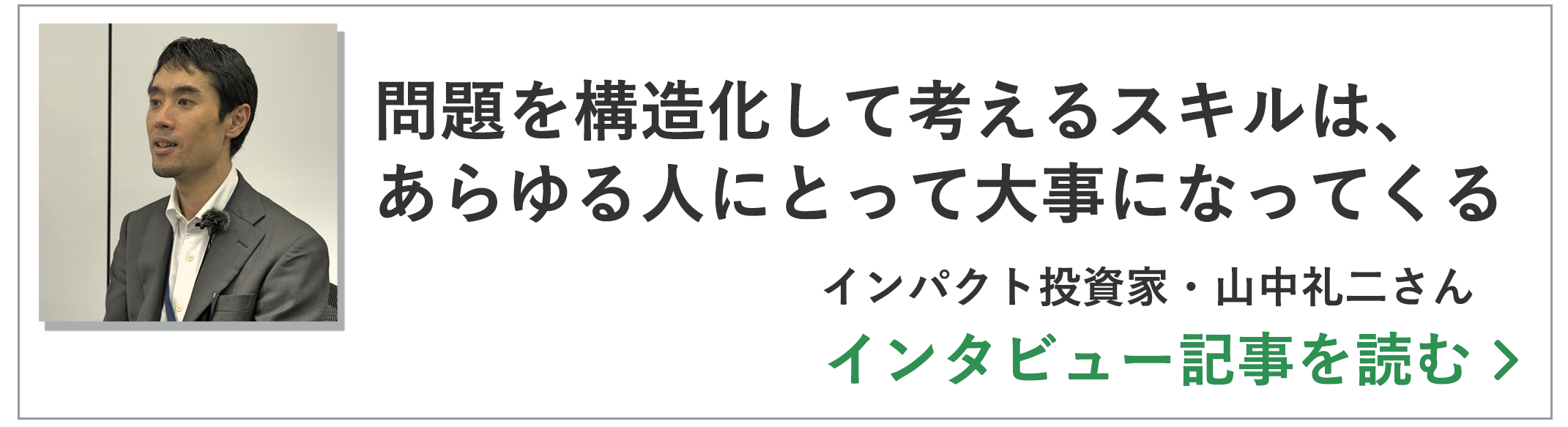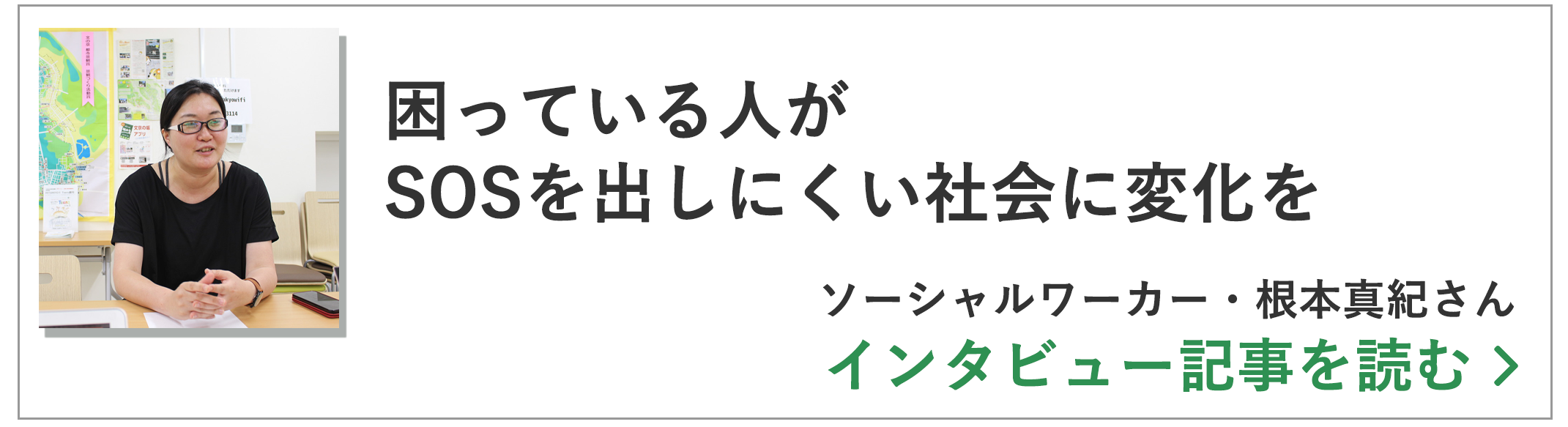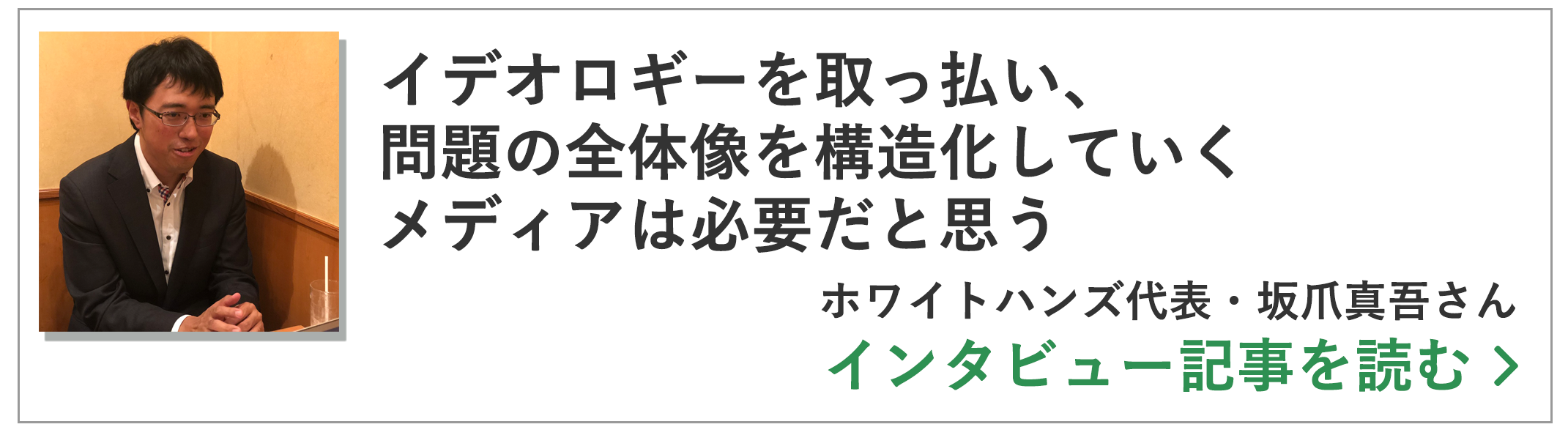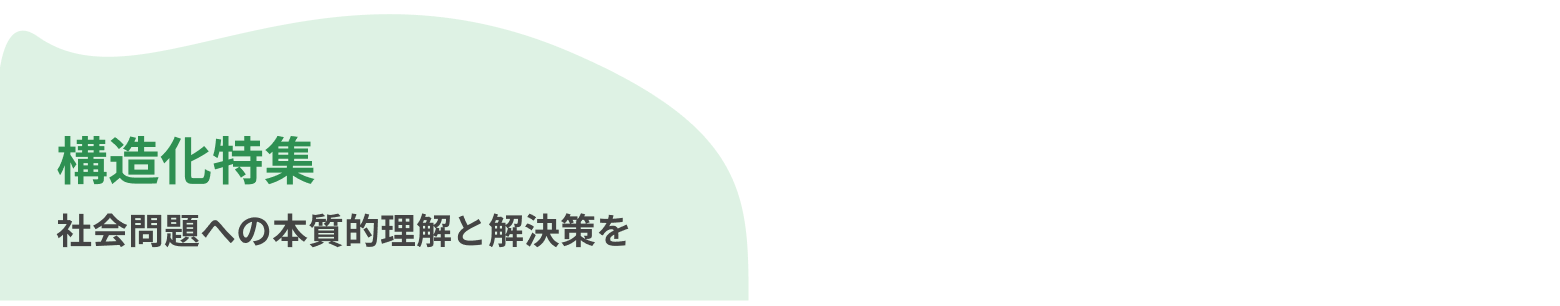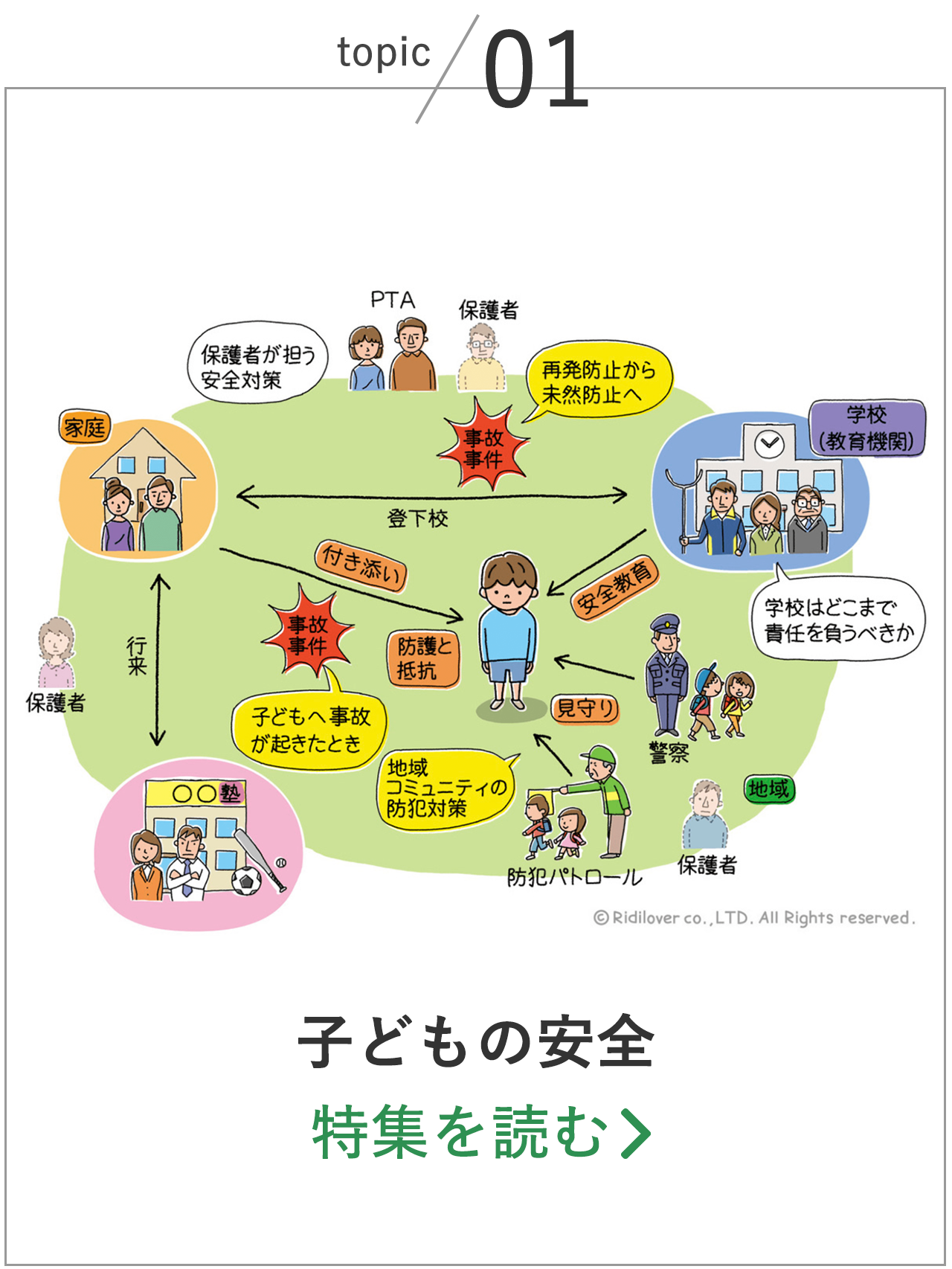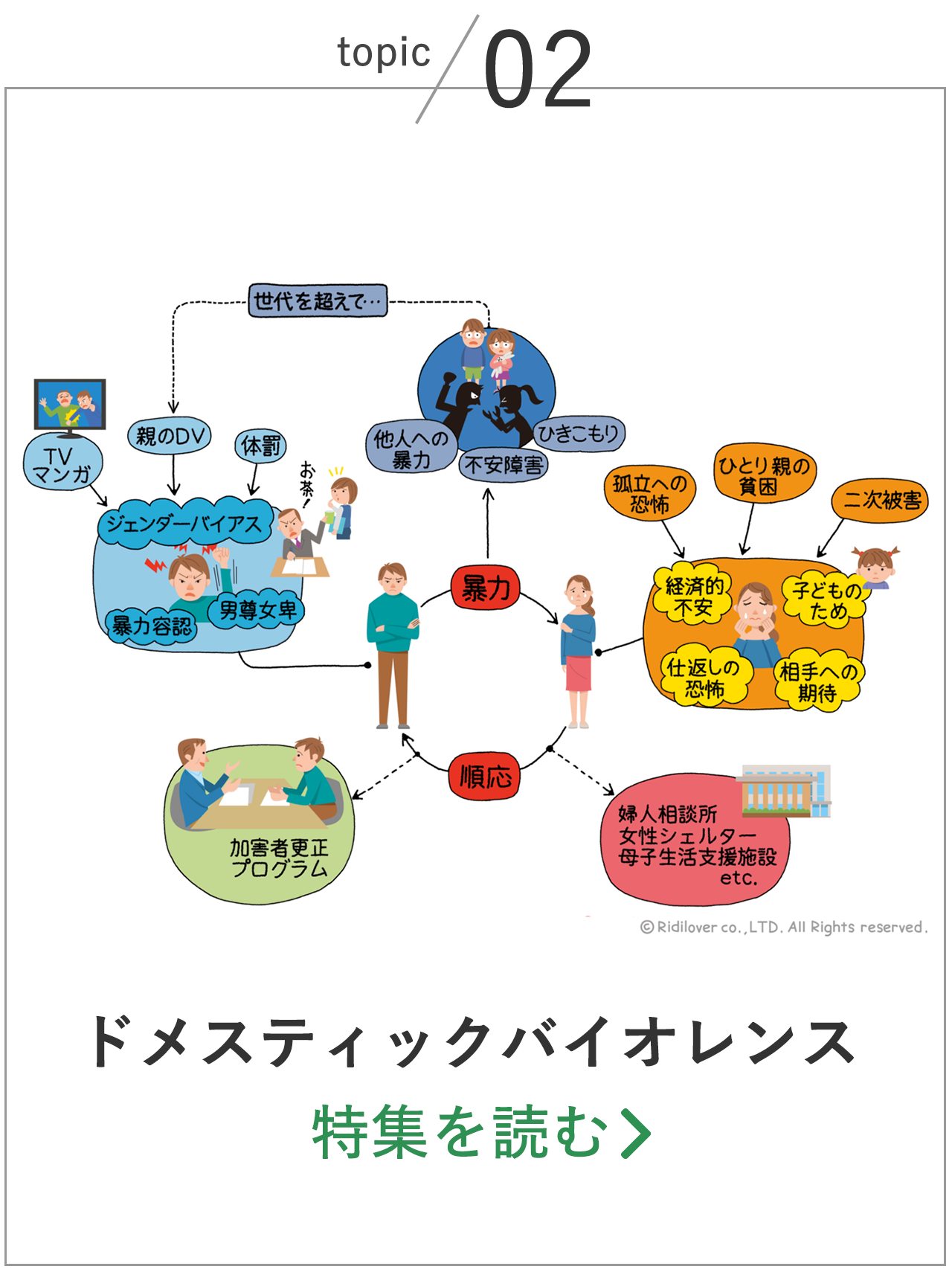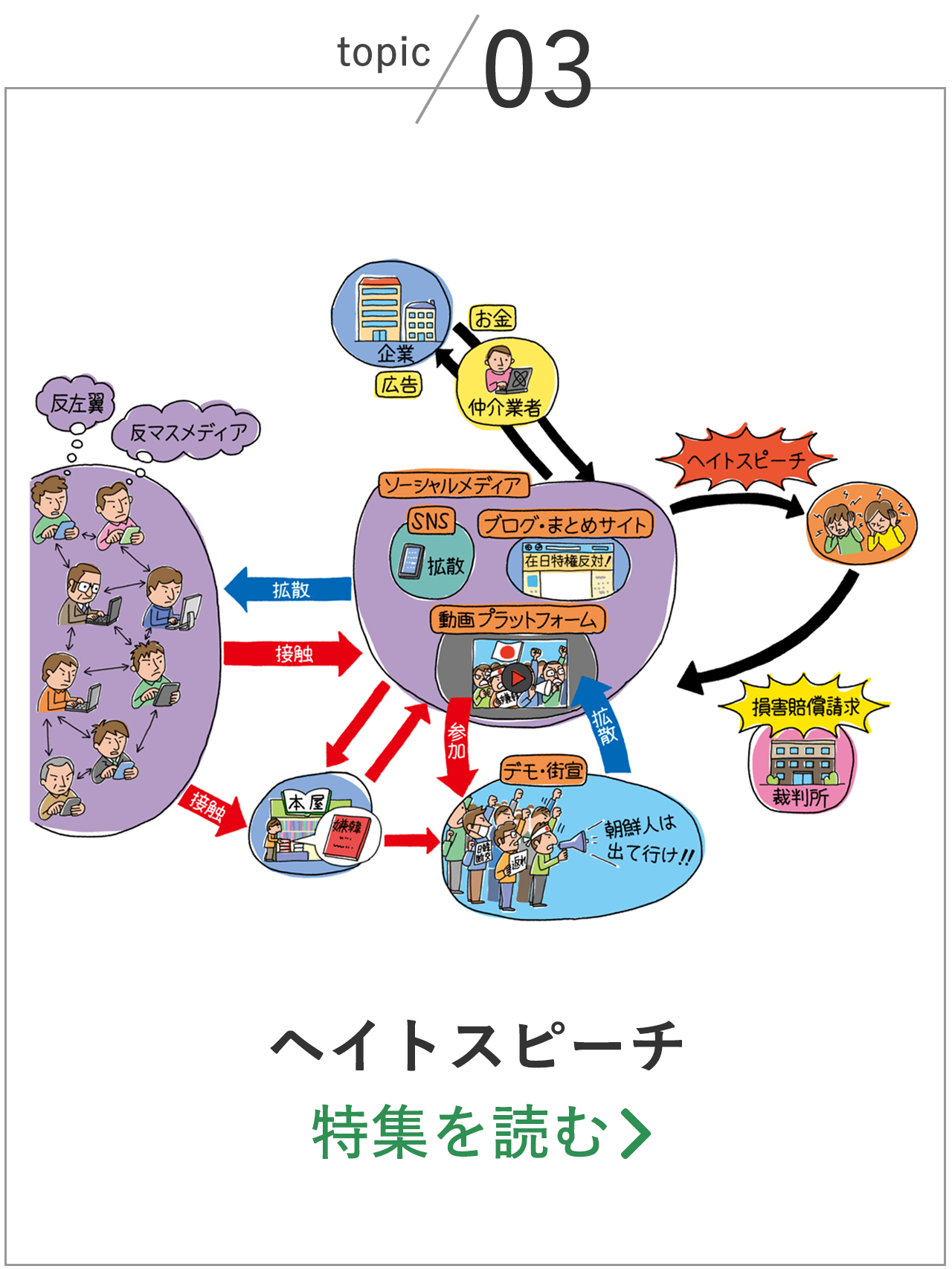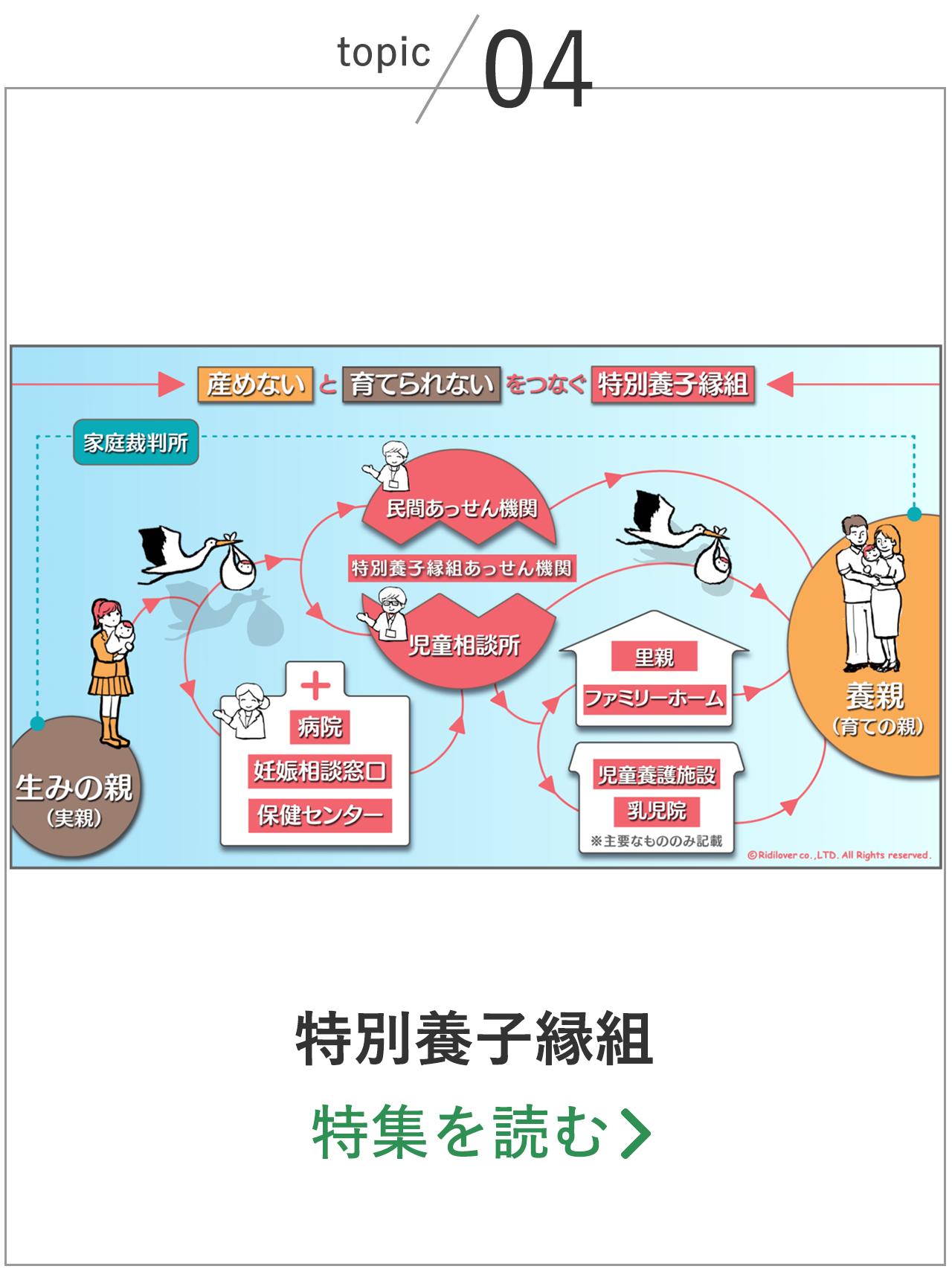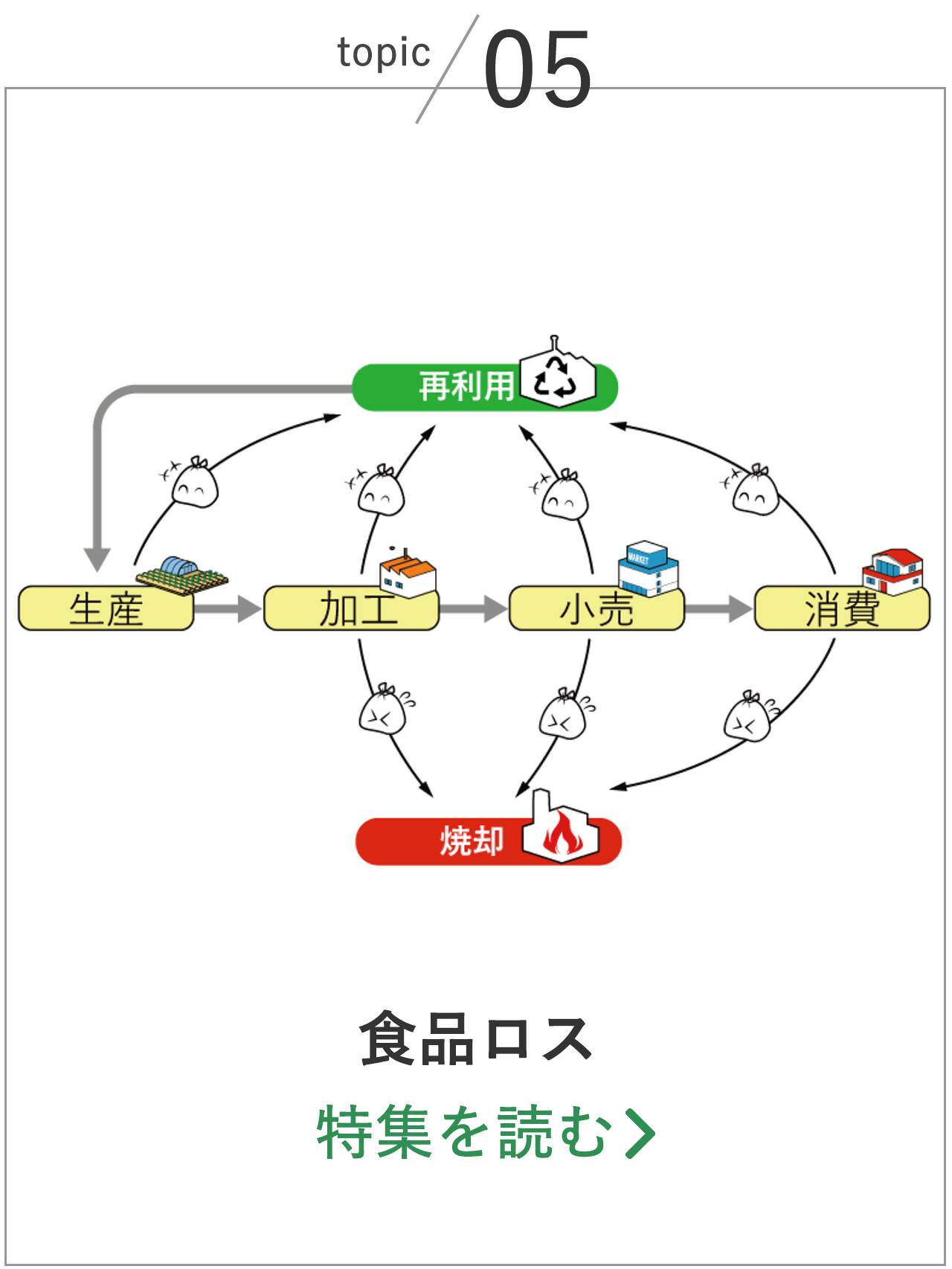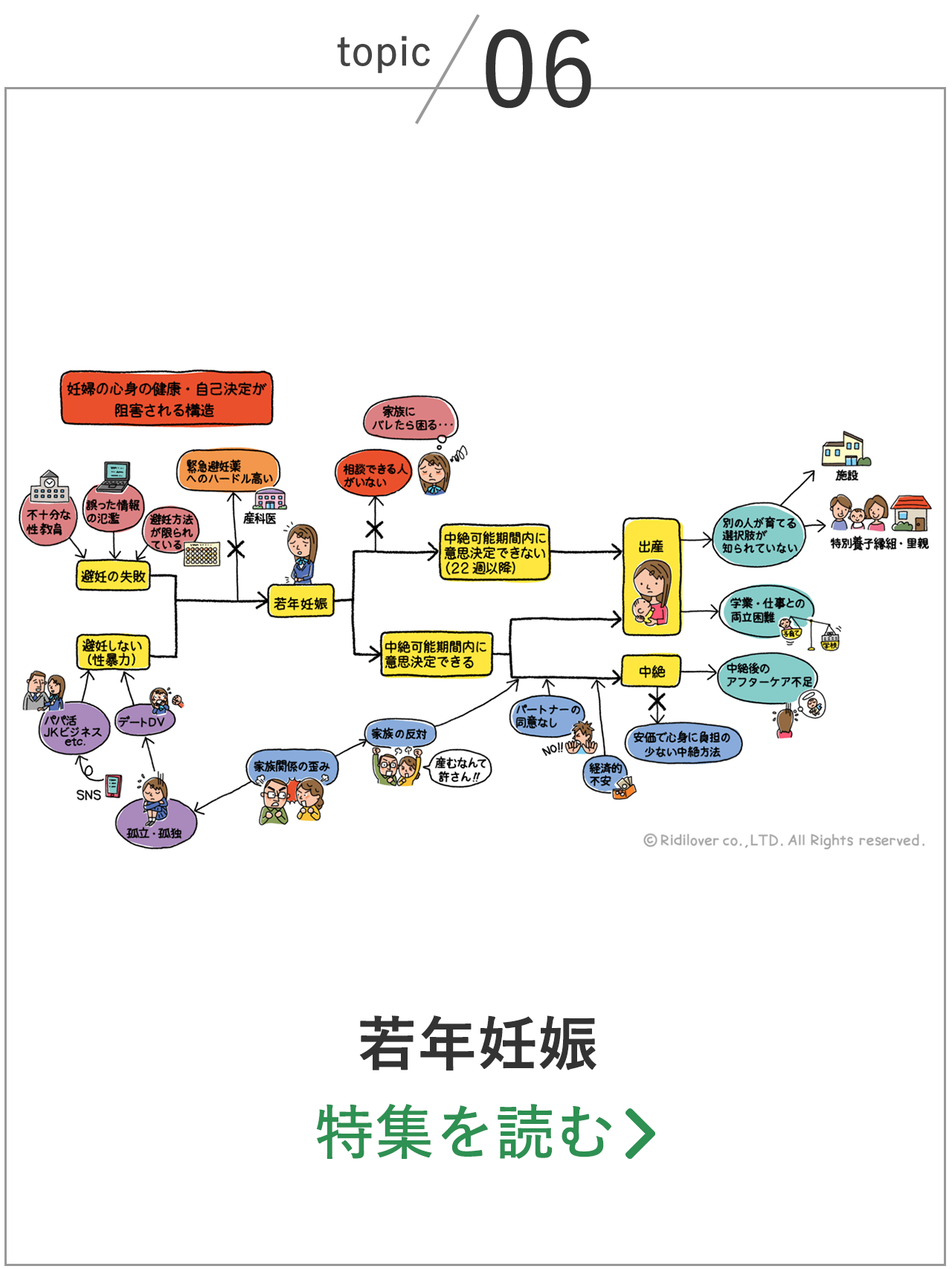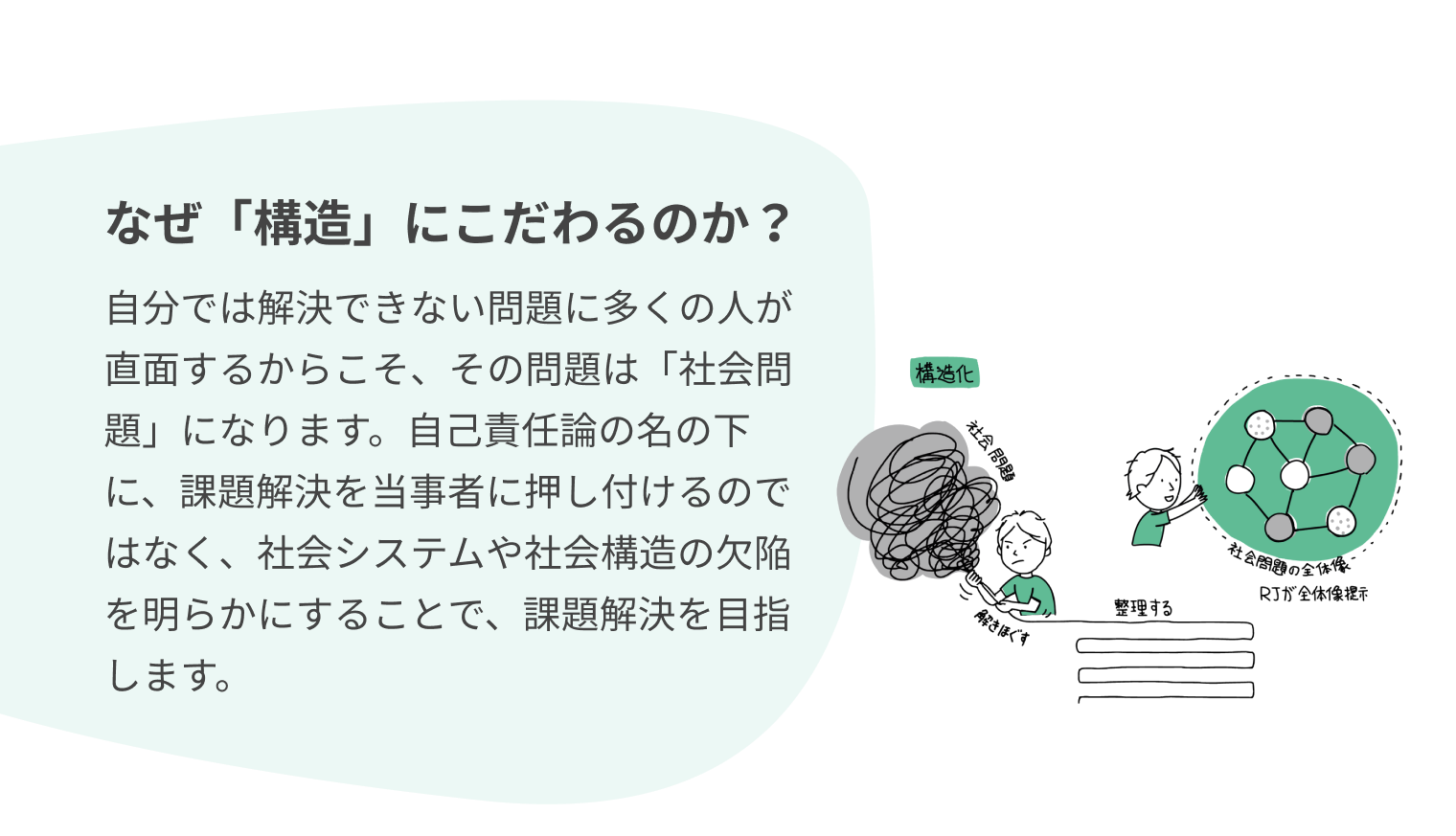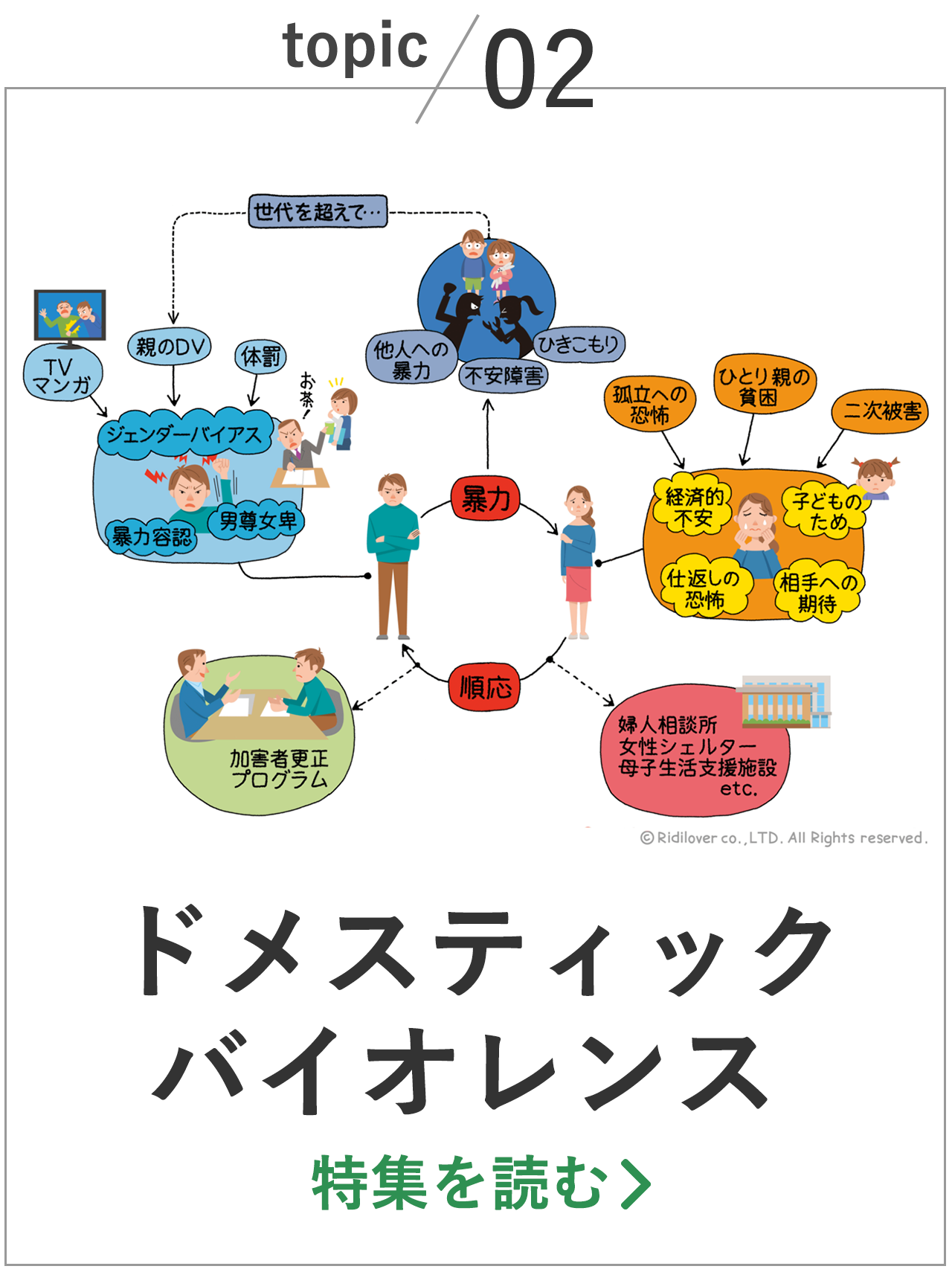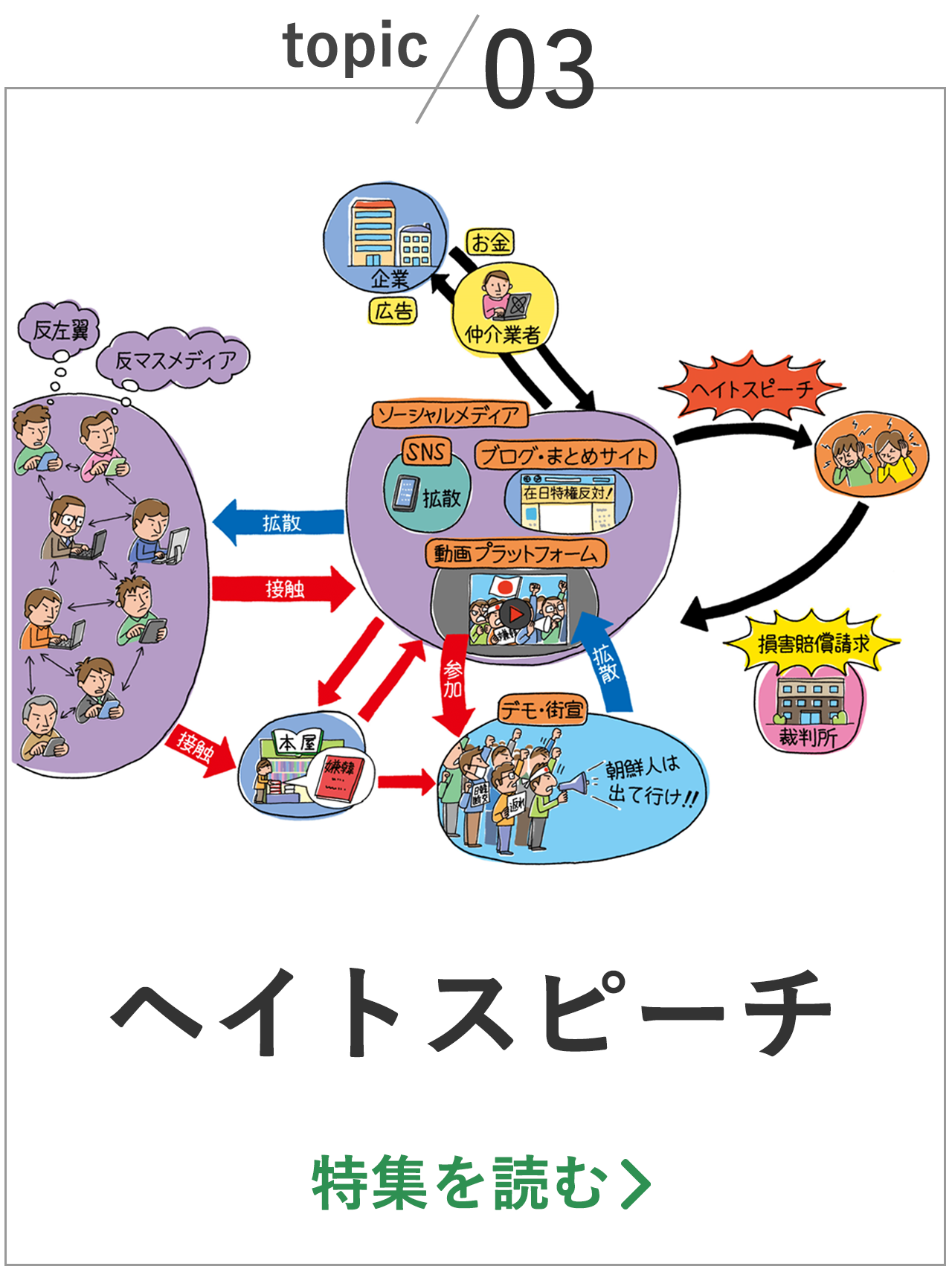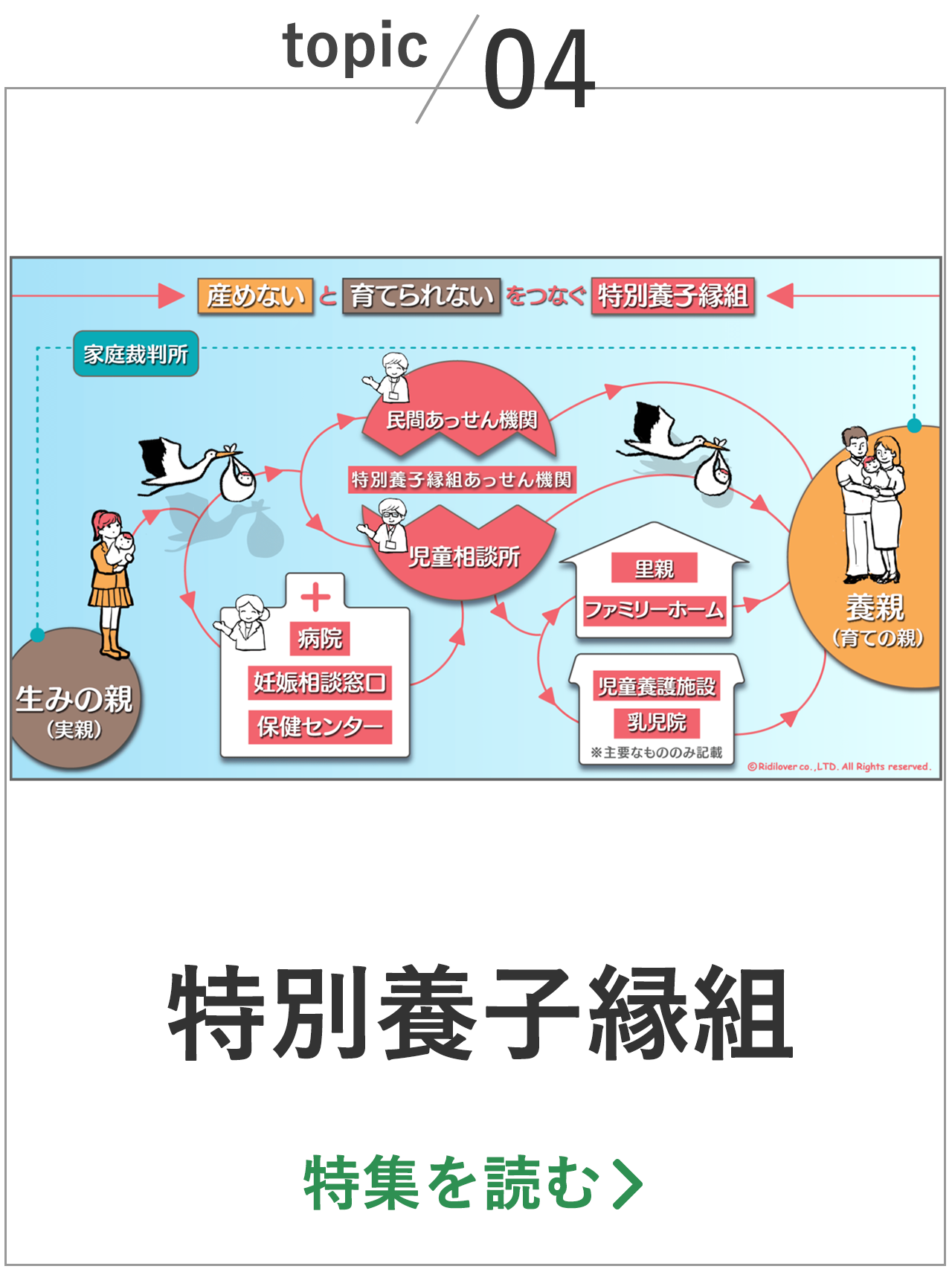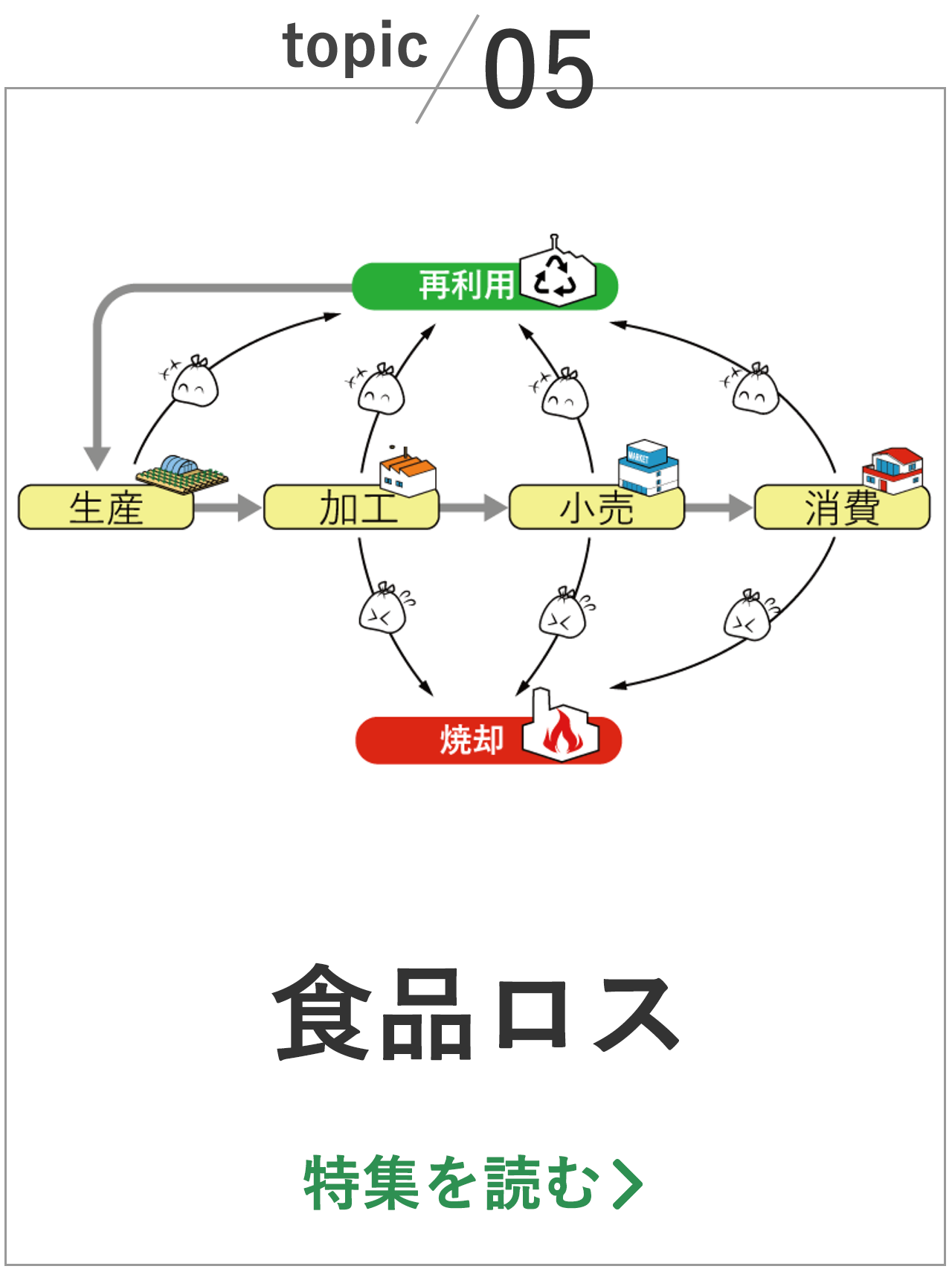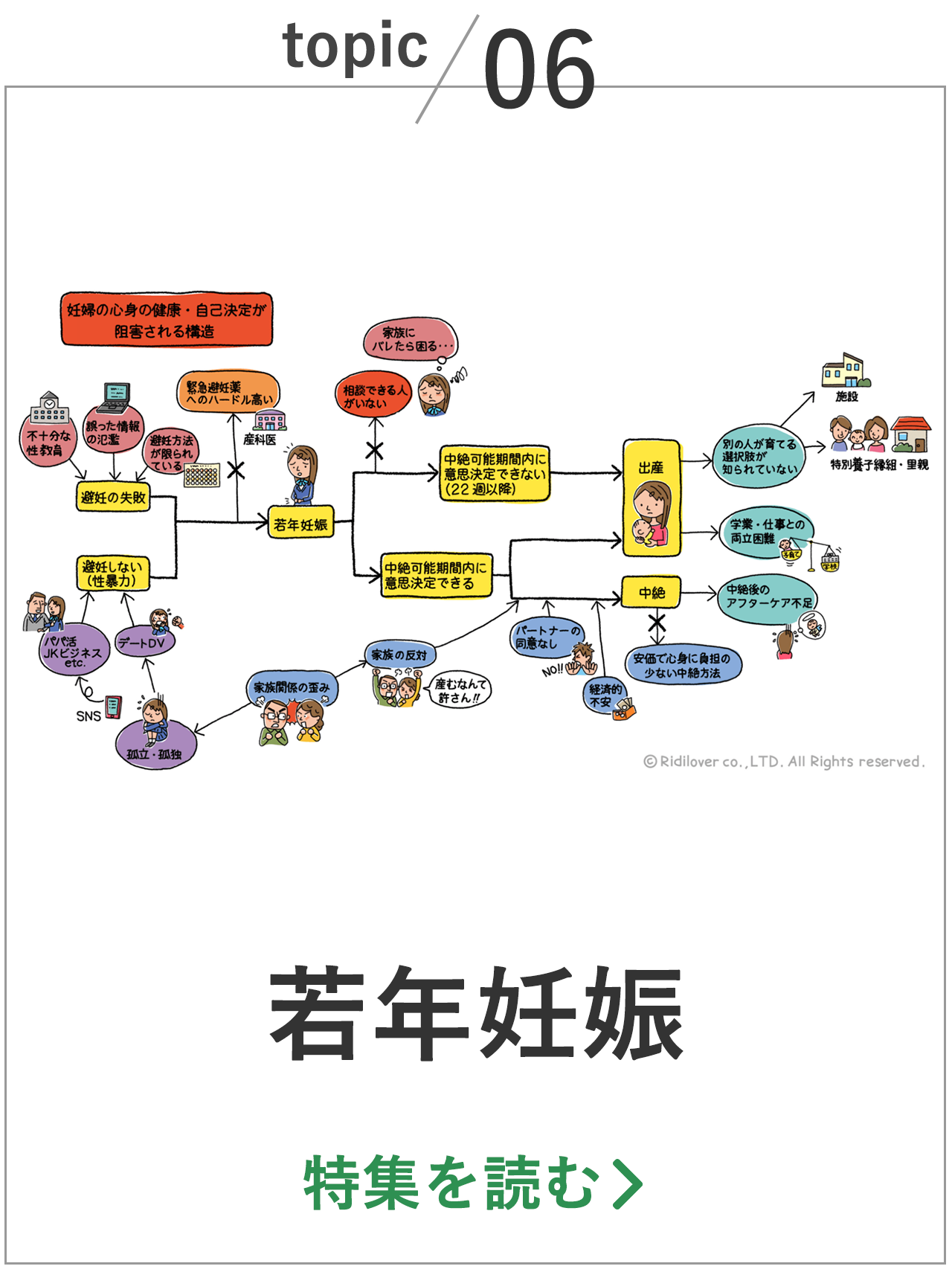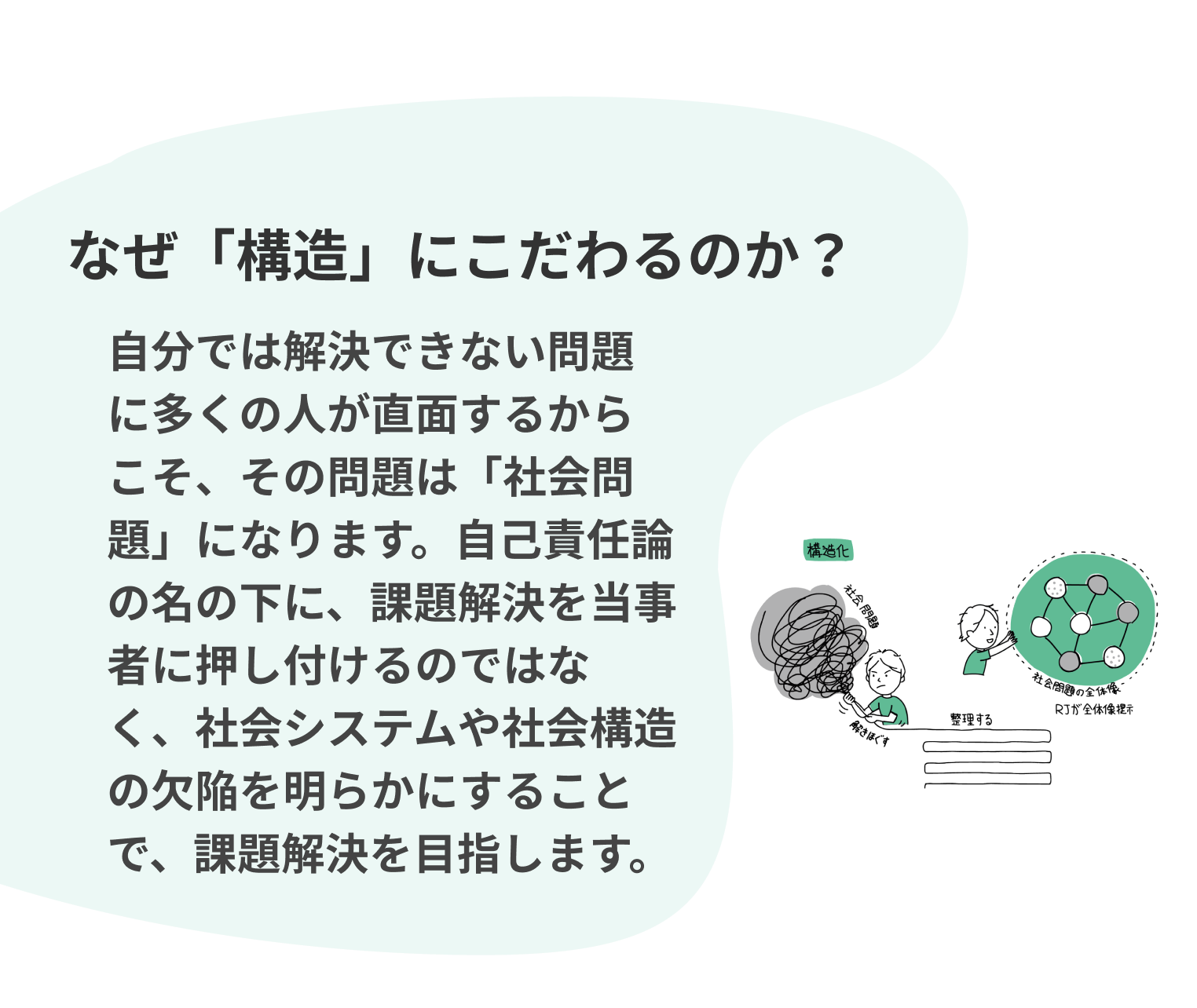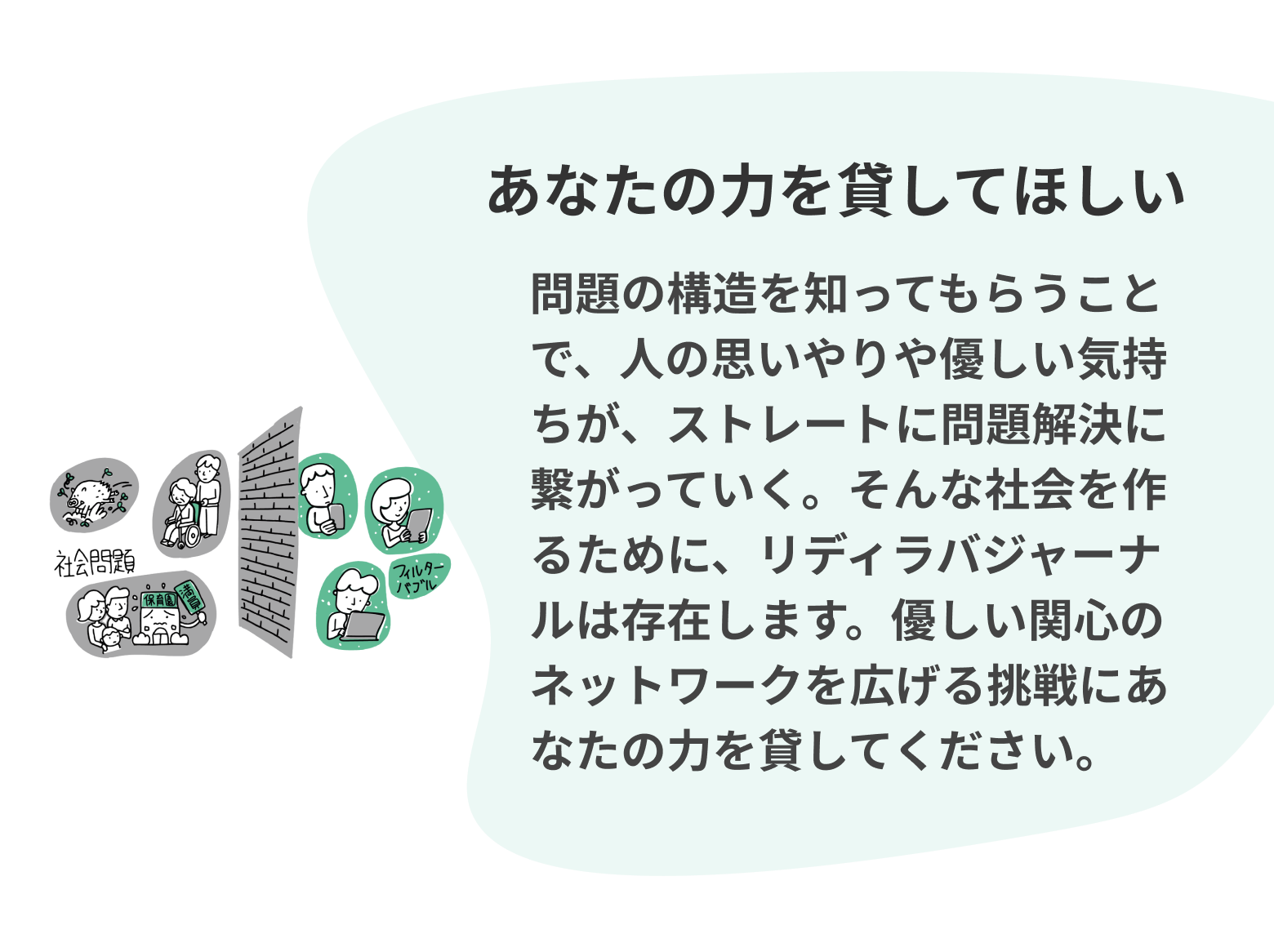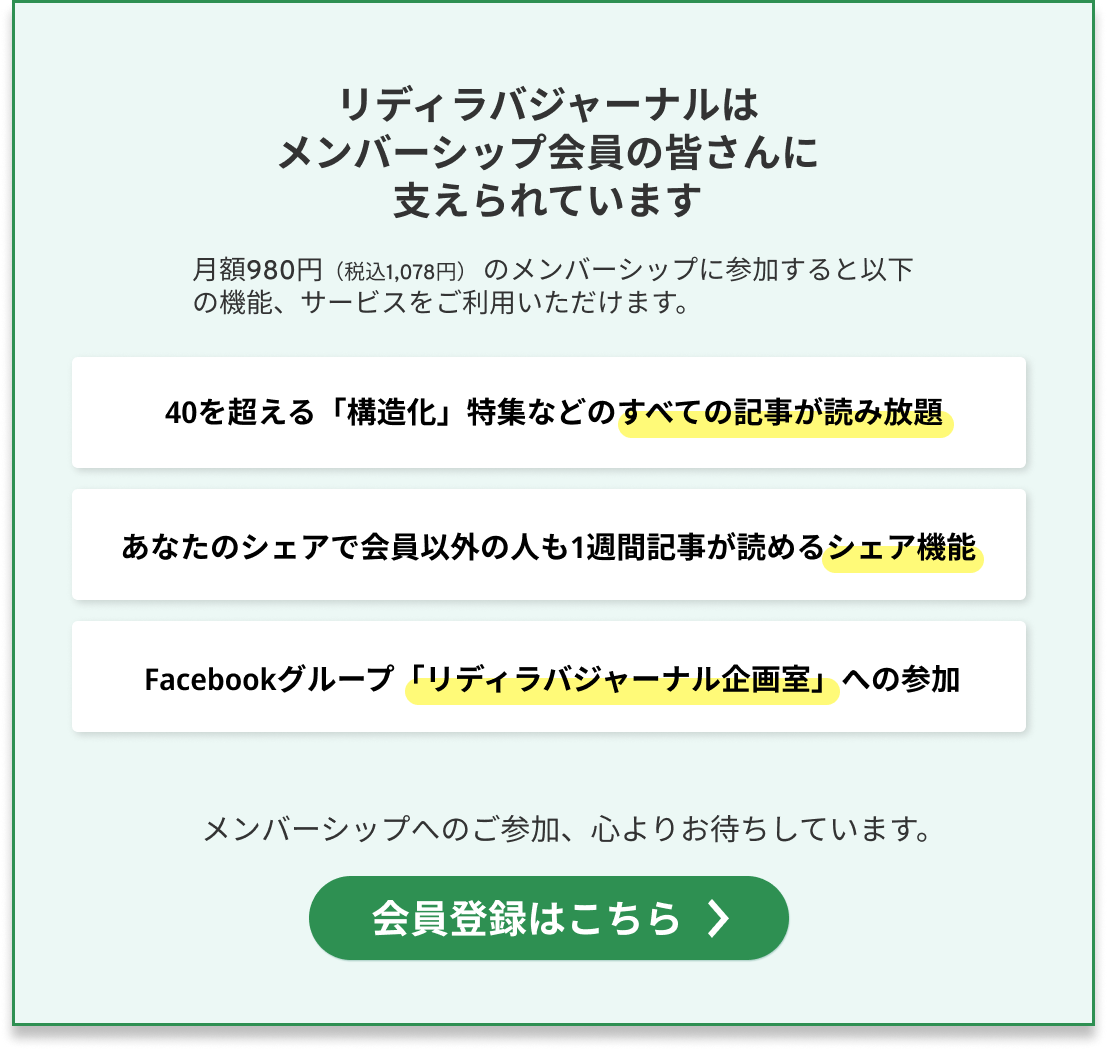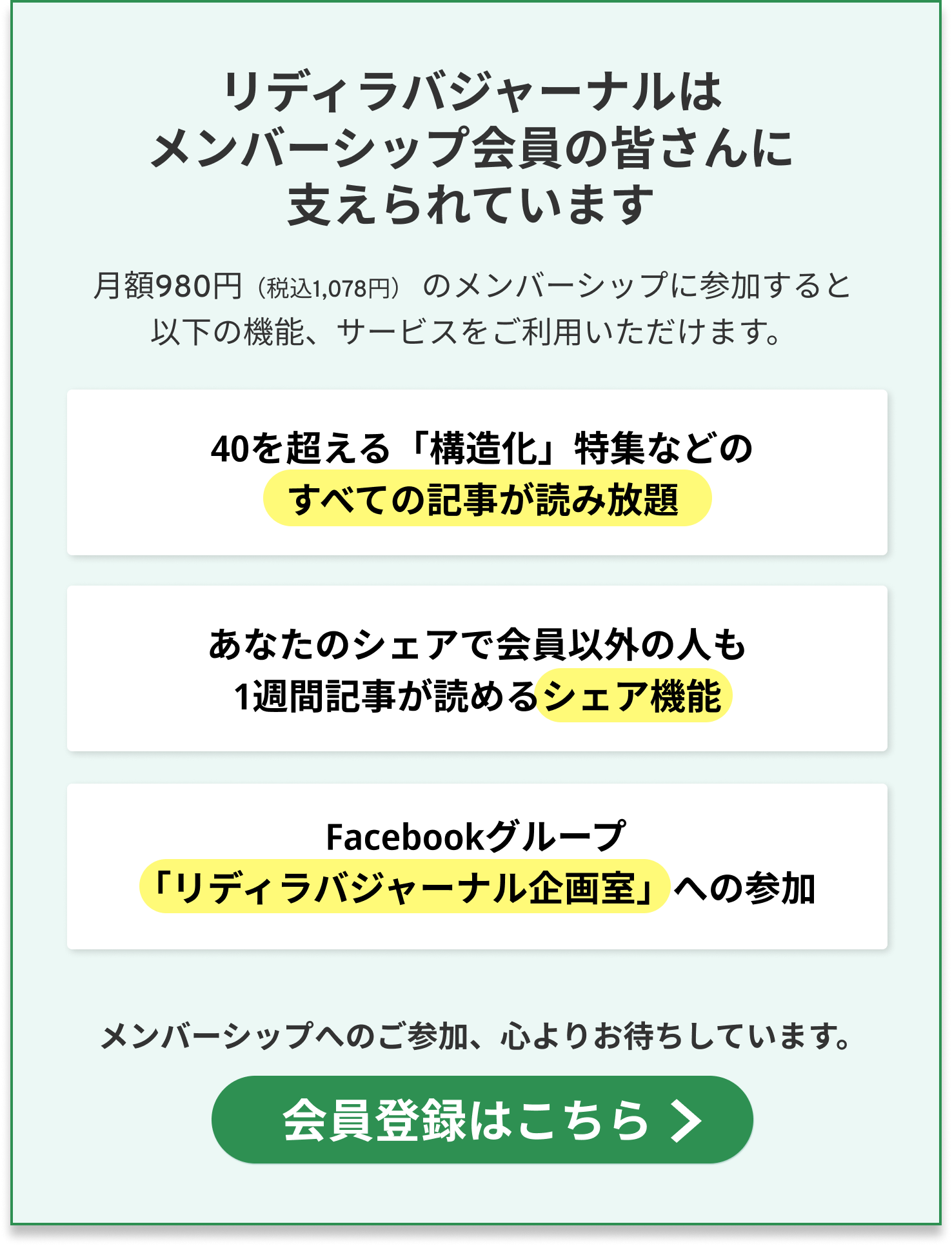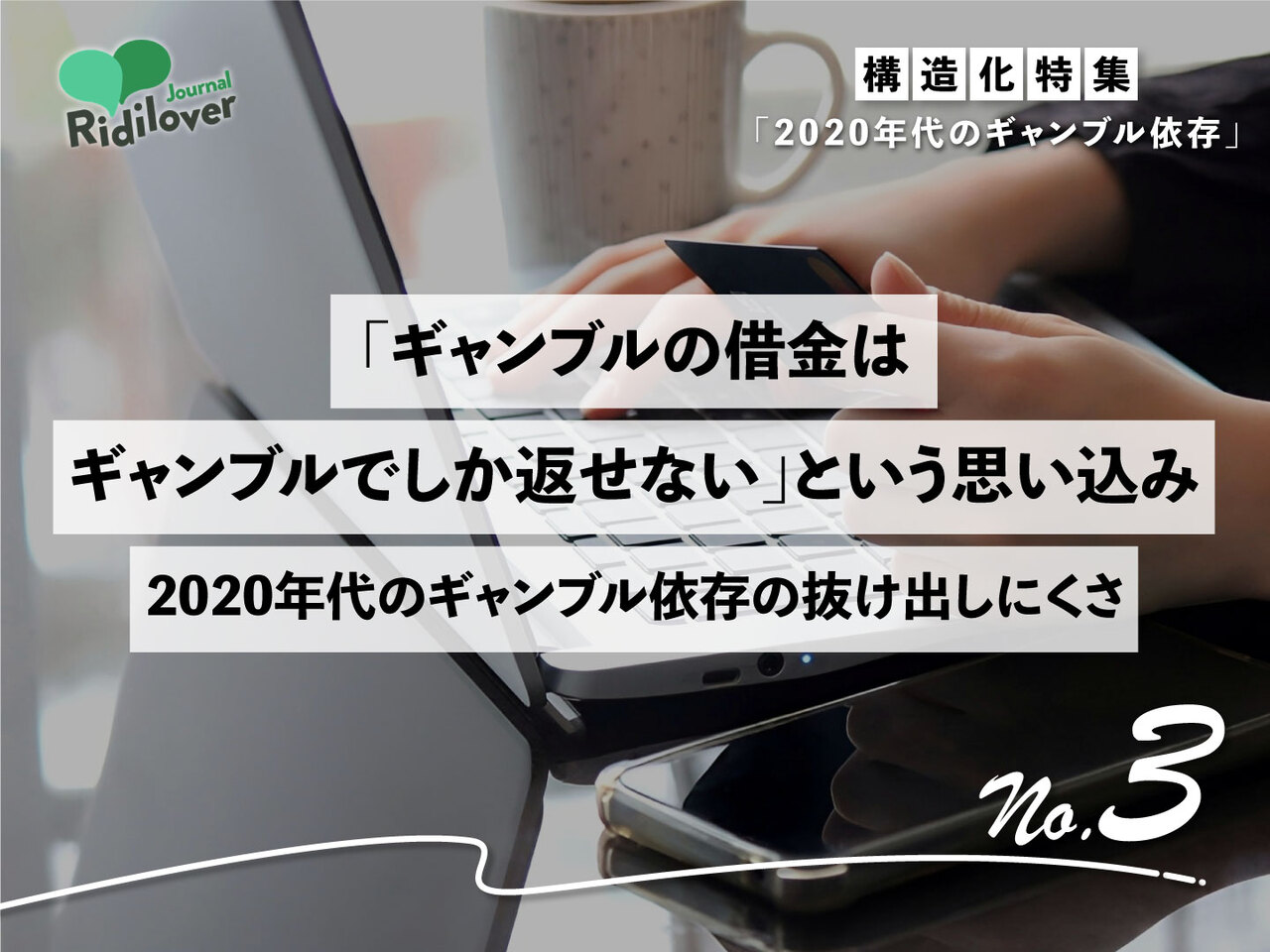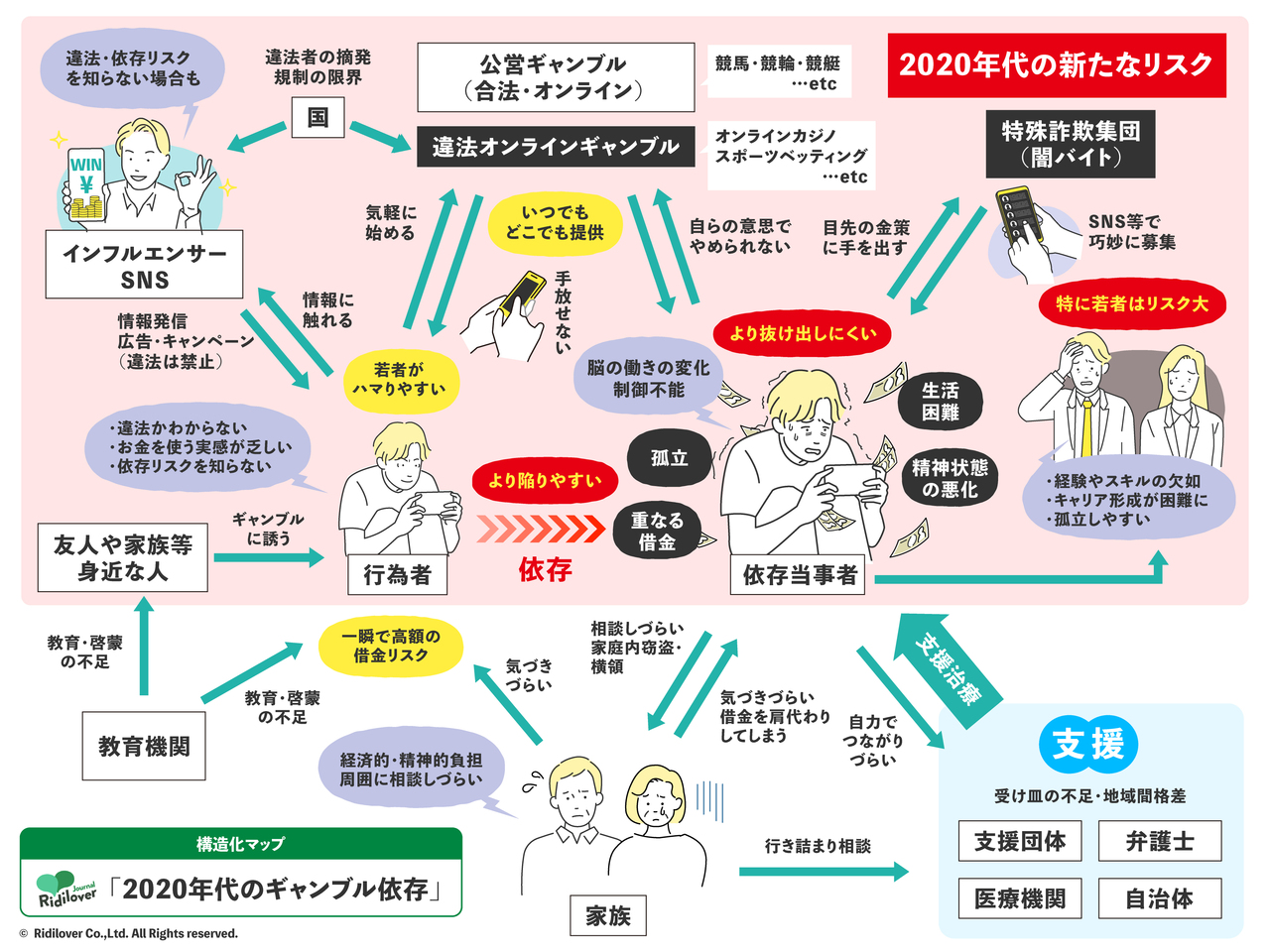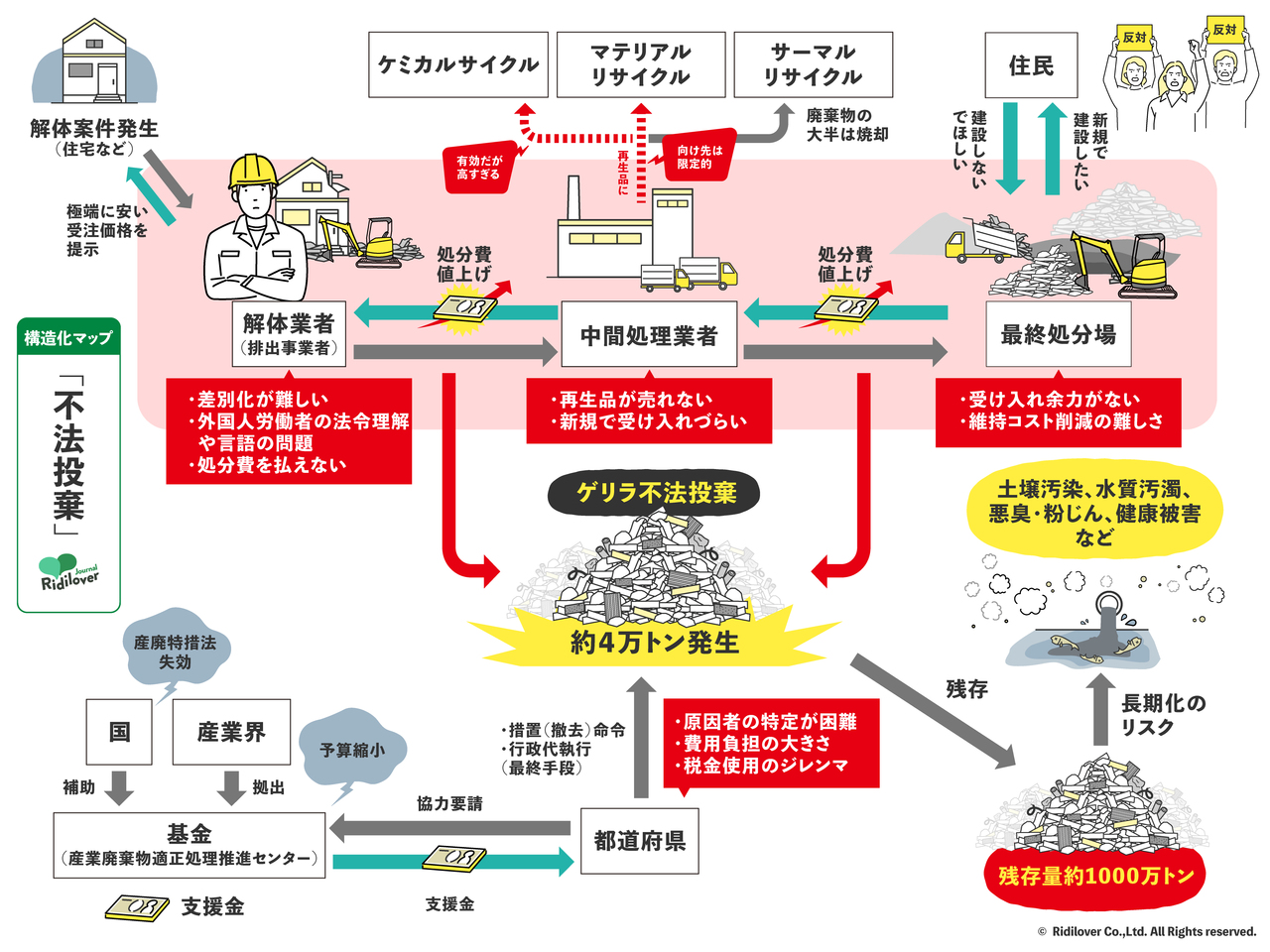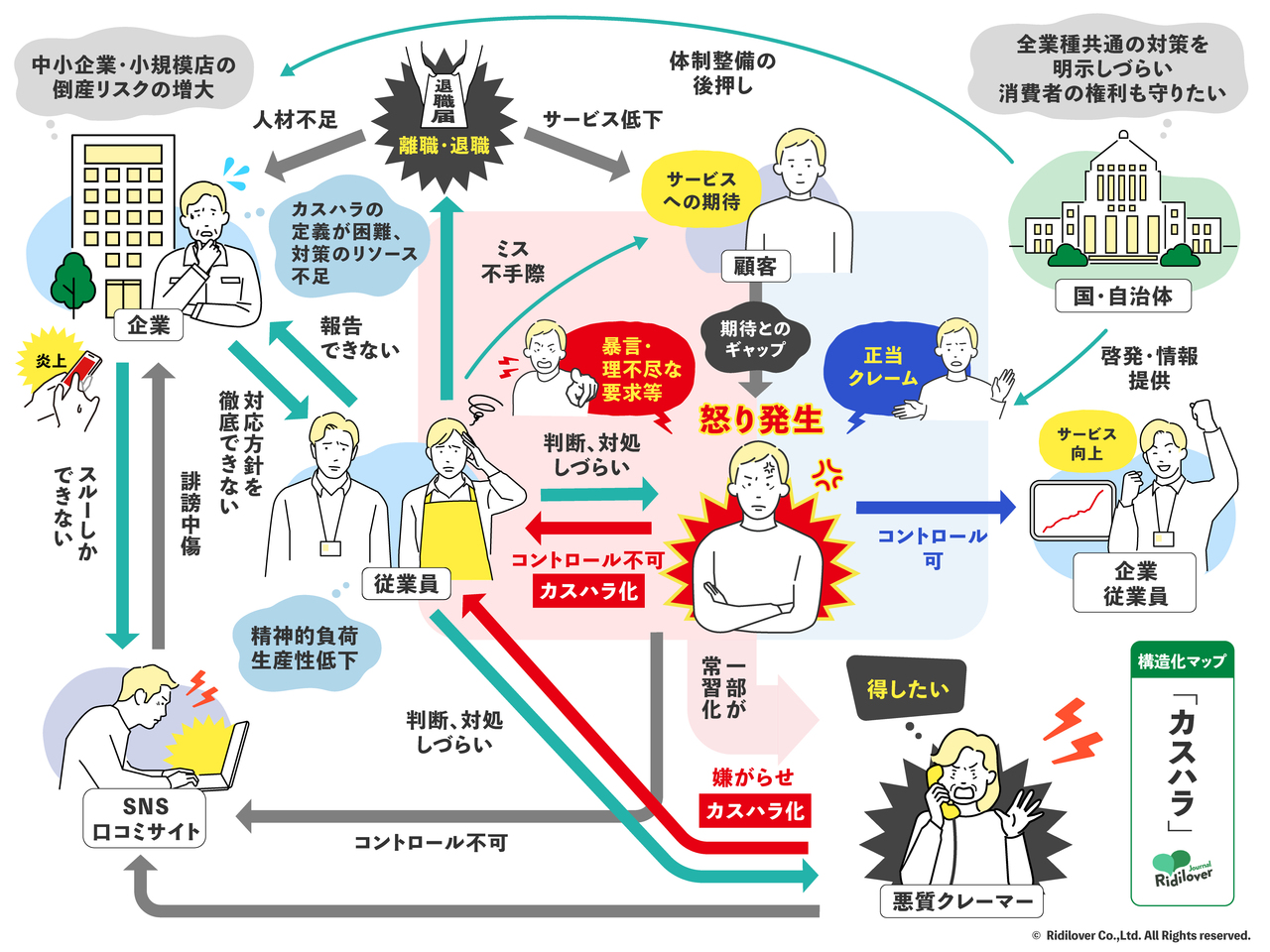2人に1人はがんを患い、3人に1人はがんで亡くなるーー。
医療技術が発達した今もなお、「がん」は日本人のQOL(Quality of Life)に大きな影響を与えている。
自分自身ががん患者になったとき、あるいは身近な人ががん患者になったとき。
私たちはどのようにがんと向き合えばいいのか。
今回の特集テーマは「がんの緩和ケア」。
川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター医師の西智弘さんは、「緩和ケアには、終末期になってからのケアという誤解があるため、緩和ケアを受けることを嫌がる患者や、『まだ緩和ケアを受けるのは早い』といった言い方をする医療者もいる」と指摘する。
「本来は、がんという病気を抱えて、これからどう生きていきたいか一緒に考えていくことが、緩和ケアのスタートなんです。ですが、痛みや精神的苦痛がひどくなってから初めて緩和ケアを受けると、すでにやりたいことができないということもあります」

緩和ケアの問題意識について語る西智弘さん(写真撮影:幡野広志さん)。
緩和ケアについて、WHO(世界保健機関)の定義(2002年)には以下のように記されている。
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティー・オブ・ライフ(QOL:生活の質)を改善するアプローチである。
本来、緩和ケアの概念には、仕事の問題や、人間関係、死への恐怖など、生きていくうえでのあらゆる苦痛を、早期に発見し、苦しみを予防することが含まれているのだ。
乳がんがきっかけで人生ととことん向き合った
26歳でステージ4の乳がんが見つかり、2017年9月に29歳の若さでこの世を去った広林依子(よりこ)さん。
デザイナーとして働いていた広林さんは、大学時代、編集長安部とともに、リディラバジャーナル運営会社リディラバのロゴをデザインしてくれた一人だ。
広林さんは自らの病気と向き合うなかで、QOLを上げるための様々なアイディアを生み出し、自らの“ライフデザイン”として、その知見や生き方をハフィントンポストで発信していた。
がんになったことで、私は自分の人生ととことん向き合って、自分自身のライフをデザインしたいと思うようになりました。
自分の居心地のいい場所をつくること、最悪の状況をシュミレーションすること、チームをつくること......。ライフデザインは究極のデザインです。
私は常に、どうより良い生活をしたいかを考えてきました。患者として弱気になるのは好きではありません。同時に、限り有る人生を思い切り楽しみ、明日死んでも悔いはないと思えるほど、納得感のある生き方が私なりにできていると感じています。
「26歳でステージ4の乳がん発覚、私が決めたライフデザイン ー強く美しくー」(https://www.huffingtonpost.jp/yoriko-hirobayashi/26_4_b_15324530.html)より引用。
彼女は病気と向き合い、ライフデザインを考えることで「納得感のある生き方」をしていたと述べている。
一方で、がんは心身に苦痛をもたらし、がんになったことをきっかけにうつ病や適応障害を発症することや、自殺へと至るケースもある。
苦しみは、病状だけではなく、他者との関係性からも生じる。
34歳でがんの一種である多発性骨髄腫と診断された写真家の幡野広志さんは、見た目が健康そうだったため、病気への理解が得られなかったことが辛かったと言う。
「親族も友人も、僕の見た目が元気そうだから『頑張れよ』と声をかけるのですが、それがとにかく辛くて。実際には体力が落ちていて日常生活を送るのも苦しい状態だったんです。医者も薬を処方してくれるけれど、理解はしてくれない。誰も自分の状態を分かってくれないという孤独があった」
がんになった経験のない人が、患者の病状や気持ちを理解することは容易ではなく、医療者や家族などがん患者を支える周囲の人々の言動が、患者を傷つけてしまうこともあるのだ。

患者の心理状態には、家族や医療者など周囲の人々や職場との関係性、社会の認識などが影響を及ぼす。
本特集では、がんを患った人の抱える苦しみを、患者と周囲の人との関係性や、社会との関係性に焦点をあてて取材。
医療者、がんを患う人などへのインタビューをもとに、病気と向き合って生きる人々の生き方、がん患者を取り巻く社会に必要なことについて、全5回にわたって見ていく。
多くの人が直接的に、あるいは間接的に関わるであろう病「がん」。
国立がん研究センターによれば、2017年のがん罹患(りかん)数予測は、約101万4000人で過去最多。
人口の高齢化によって、がんになる人は今後も増えていくと予想されている。
自らが病気になったときに納得感のあるライフデザインを描くために、あるいは、病気になった人の苦痛を和らげるサポートをするために、いま私たちには何ができるのか。
本特集がそれらの問いを考えていくきっかけになれば幸いだ。
第一章は【当事者と医療者】。

34歳でがんの一種である多発性骨髄腫と診断された写真家の幡野広志さん。
第一回【「がん」になって感じた孤独】では、がんと診断されたときの病気の受け止め方や、医療者のコミュニケーションについて見ていく。
第二章は【患者を支える人】

(Chinnapong/Shutterstock.com)
第二回【「頑張れ」はNG。善意の声がけも時には刃に】では、がん患者に対してどのように接するのか、周囲の「支え方」について考えていく。
2人に1人はがんになる時代。身近な人ががんになったら、あなたはどのような言葉をかけるか?
第三章【社会との関係性】

第三回【納得いく生き方を選択するための「緩和ケア」】では、がんになったときに納得いく選択をするために必要なこと、緩和ケアの果たす役割を考える。
第四回【2人に1人はがんになる時代。がん患者が生きやすい社会を】では、がん患者に優しい社会のあり方とはどのようなものなのか、考えていく。見た目が健康そうであっても実は立っていることが辛いこともある、そうした患者の声を伝える。
第五章は【安部コラム】

第五回【安部コラム「がん患者というラベリングに引きずられない」】では、リディラバジャーナル編集長の安部が、みずからの体験にもとづき、患者の意思決定と他者との関係性について考えを綴る。