LGBTQ・障害・ひきこもり 「いないこと」にされてきた人たちが語る「D&I」の課題

LGBTQ・障害・ひきこもり 「いないこと」にされてきた人たちが語る「D&I」の課題
「リディフェス」セッション動画&記事は特設ページにて公開中!
⇩特設ページはこちら⇩
「まさか自分の周りに性的マイノリティはいないだろう。マイノリティの人たちは、『いないこと』にされてきたと思うんです」
自身がゲイであることをカミングアウトし、性的マイノリティに関する情報発信などに取り組む一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣さんは、このように語る。
近年、様々な場面で見聞きするようになった「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」。
女性管理職の割合にコミットメントを示す企業が現れるなど、D&Iを掲げた取り組みは広がっているようにも見える。
しかし、冒頭の松岡さんのコメントのように、社会で困難を抱えるマイノリティの全てが可視化されているわけではない。
自身のお子さんが障害を持って生まれたことをきっかけに、障害者の経済的自立をテーマに活動するNPO法人AlonAlon 理事長の那部 智史(なべ・さとし)さん。
自身のひきこもり経験から、ひきこもり当事者による発信活動などを行う、一般社団法人ひきこもりUX会議 共同代表理事の林恭子さん。
当事者としての体験をもとに課題解決に取り組む3名が、THE CREATIVE FUND, LLP代表パートナー小池藍さんのモデレートのもと、D&Iをテーマに議論を重ねた。
「国や自治体が協議会を作っても、そこに当事者はいない」
「健常者だって障害者だってみんな同じなんだから、一緒になってお金儲けして何が悪いのか」
「ひきこもりの人の多くは『普通になりたい』って言います。多くの人が思う『普通』の姿になれなければ駄目、という社会の空気がある」
自身の体験、そして支援を重ねてきた当事者の声を基に、D&I推進のポイントを議論する。
いきなり「フルタイムで働け」
D&I推進を妨げる「選択肢」の問題
小池藍 モデレータを務めます、小池藍と申します。
私自身、女性比率が世界でも2%と言われる投資業界で長年働いてきた経験も踏まえて、3人のお話を聞いていけたらと思います。
ではみなさん、自己紹介をお願いします。

(小池さん)
那部智史 那部智史と申します。
私の息子は重度の知的障害を持って生まれてきました。息子の目線で世の中を見てみると、社会のアンフェアな部分がたくさん見え始めました。
40歳の頃、ビジネスの世界から未経験の福祉の世界に飛び込んで、「就労継続支援B型事業所」と呼ばれる福祉施設を運営しつつ、障害者の経済的自立をテーマに活動しています。
林恭子 林恭子と申します。
私は高校時代の不登校と、その後30代の後半まで断続的に約20年間引きこもっていた経験があります。
もう一度、この社会で生きてみようと思えるまでに20年かかりましたが、自身の経験を活かしつつ、ひきこもり当事者の方々の声を届ける活動をしています。
私が共同代表を務めるのは「ひきこもりUX会議」という団体なのですが、「UX」とは「Unique Experience」の略です。
ひきこもりはネガティブに捉えられがちで、実際に辛いことはたくさんあるのですが、その経験こそが誰かを救ったり、より良い社会を作ったりする助けになるかもしれない。一人ひとりの、ユニークな体験なんだとのメッセージを込めています。
松岡宗嗣 松岡宗嗣と申します。
私はいわゆるゲイと呼ばれる性的マイノリティの当事者です。
性的マイノリティが生活を送る上での課題はたくさんありますが、ひとつに「カミングアウト」の問題があります。
自身のセクシュアリティを他人に伝えることで、いじめや自殺、会社でのハラスメントなど、本当に様々な不利益を被る状況があります。
少しずつ社会が変わってきているとは思いますが、それでも多くの人は性的マイノリティの問題に無関心だったり、当事者を無意識に傷つけてしまったりすることがあります。
個人の意識改革も進めながら、同時に政策や制度の側を変えていく、支援の仕組みを作ることが大事だと思い、性的マイノリティの政策・制度について情報発信を活動の中心に据えています。
小池 領域は異なれど、現場の最前線で多様性・社会包摂というテーマと向き合っているみなさんですが、まずはD&Iという言葉はどう映るのか、D&Iと聞いてどんなことを考えるのか、聞かせてください。
林 私はD&Iを「選択肢」という観点から考えています。
最近、不登校児童の数が24万人を超えて、過去最高と報じられました。
子どもの数は年々減っているのに、不登校は増えている。子どもたちにとって学校が安心できる、楽しめる場ではなくなっているんですよね。
では、子どもたちに学校以外の居場所や学びの場があるかというと、選択肢はほとんどありません。学校に行かなければもう他に行き場がないんですよね。
選択肢の少なさは、ひきこもりの問題にも当てはまります。本人たちは誰よりも、このままではいけないと思っているし、働きたいと思っている人も多いです。
ただ、頑張って仕事を探そうと思って、就労支援に繋がっても、いきなりフルタイムで週5日間働けって言われるわけです。長年引きこもってる人からすると、それはさすがに無理だよとなってしまう。
今の社会の中には選択肢が限られていて、私は働き方や学び方、生き方にもっと多様な選択肢が必要だと思うんです。
ひきこもりや不登校は、「怠惰だ」「努力不足だ」と当事者の自己責任にされがちですが、私は当事者ではなく、社会のあり方が問われている問題だと思っています。

(林さん)
「当事者を救うはずなのに」
支援制度に見える矛盾
小池 那部さんは、D&Iについて、どんな問題意識をお持ちですか。
那部 私は、本来当事者を救うはずの支援制度が、むしろ当事者の社会参画を妨げている側面があると思っています。
私は今「就労継続支援B型事業所」という施設を運営しています。障害を持った方が、一般就労に移行する前の訓練の場所だとイメージいただけるとわかりやすいかと思います。
このB型作業所は、全国で30万人弱の障害者が利用しているのですが、平均の工賃(給与)は月額16,000円、一般就労への移行率は年間で1.5%です。
小池 工賃も就労への移行率も、そんなに低いんですか。
那部 そうです。この実態を知って、私は「障害者が稼いで暮らす権利を剥奪されているんじゃないか」と思ったんです。
障害者が稼げない、能力がないのではなくて、制度によって「稼げない仕組み」に組み込まれているんじゃないかと。
B型事業所のビジネスモデルをすごく端的に説明すると、施設に通って作業をした人数によって、国からお金がもらえる仕組みです。
今日は10人が施設に来て作業をしたので、5,000円×10人で50,000円が国から支払われる、という感じです。
実際はもっと複雑で、例えば重い障害を持つ方を受け入れたり、送迎サービスをつけたりすると、より多くの額が国から貰えますが、施設に通って作業した人数が基本の収入になります。
ですので、施設に通う障害者が就労を実現するということは、もう施設に来なくなり、日々の収入が減ることになります。
就労が実現された場合、事業所には国から追加での支払いがあるため、就労のインセンティブが無いわけではありません。
ただ、就労をせずそのまま施設で作業を続けてくれる方が、トータルとして貰える額が大きくなるので、多くの事業所はそこまで就労を推進していないのが実態だと思います。
実際、全国にあるB型事業所のうち、8割以上が1年間に1人も就労移行者を生んでいない、というデータもあります。

(那部さん)
小池 既存の制度においては、事業所の利益と、当事者のステップアップが必ずしも一致しないわけですね。
那部 当事者の利益と事業所の利益がマッチしない仕組みに、福祉業界は慣れてしまっているように感じます。
私はこの仕組みがおかしいと思って、自分で実例を作るためにB型事業所を立ち上げました。
工賃も高く、就労率も高くなるようなモデルを構築したところ、長く福祉業界にいる人たちから、「障害者で金儲けしてるんじゃないですか」と口々に言われました。
私は「障害者と一緒にお金儲けしてるんですよ」と説明するわけです。障害者だって健常者と同じように暮らせる社会を目指すんじゃないんですか、だったら一緒にお金儲けをして何が悪いんだと思います。
松岡 今のお話を聞いて、マイノリティの人たちが、お金を稼いで暮らす経済の仕組みから疎外されている問題はその通りだなと思う一方で、性的マイノリティの文脈でもよく目にする「落とし穴」があると思ったんです。
例えば、企業がD&Iを推進しようと思って採用を強化して、蓋を開けてみると採用されているのは、高学歴の男性のゲイの方が多かったりすることがあるんですね。
一方で、例えばなかなか学校に通えなくて、ひきこもりを経験していて、フルタイムで働くのが難しいトランスジェンダーの人がいたとして、その人を会社がD&Iを掲げて採用するかと言うと必ずしもそうではない。
既存の経済システムをそのままに、その中にマイノリティを組み込むという考えではなくて、フルタイムで働くのが難しい人がいるならば、多様な働き方を模索するなど、既存の制度や文化などシステム自体を見直すという考えが必要だなと思います。

(松岡さん)
「厚労省が変わった」
背景にはひとりの当事者が
林 那部さんのB型事業所の話を聞いて、既存の制度が当事者不在のまま作られている現状があるなと思いました。
不登校やひきこもりも、これまで国や自治体が協議会のようなものを作り、政策や制度の議論をしてきました。しかし、その議論の場に当事者はいなかった。
ここ数年、ようやくそういった会議体の中に当事者が入れるようになりましたが、それでも20人の委員の中で1人とかで、あとは専門家や研究者が占めています。
那部 私も、当事者の力を信じて活用していくことが、これからのキーワードだと思っています。
私が取り組む障害者の問題は、厚生労働省が管轄をしています。
厚労省の中にも役割分担があり、障害者「福祉」の領域は旧厚生省側が、障害者「就労」の領域は旧労働省側が管轄していて、この両者の連携がスムーズに行かないケースも多々ありました。
私のように、福祉から就労の間を繋ぐ活動をしていると、両者の連携不足は死活問題なんですが、この数年、厚労省内で変化が生まれ、お互いの連携が急速に進んできたんです。
なぜかと思って聞いてみると、障害を持ったお子さんのいる職員の方が、ものすごい心血を注いで、両者の狭間を埋めていったそうです。
厚労省の事例に限らず、当事者やその家族・支援者が活躍できることの重要性を、様々な場面で感じています。
林 今、まだ本当に数はわずかですが、当事者自身が活動を行う流れが生まれています。
当事者会を作ったり、自治体と一緒にイベントをやったり。でも、当事者の活動に対する支援はまったくありません。
当事者たちの活動を支援し、一緒に作っていくようなあり方が、いま求められていると思います。
松岡 私も同感で、KDDIさんの事例を思い出しました。

































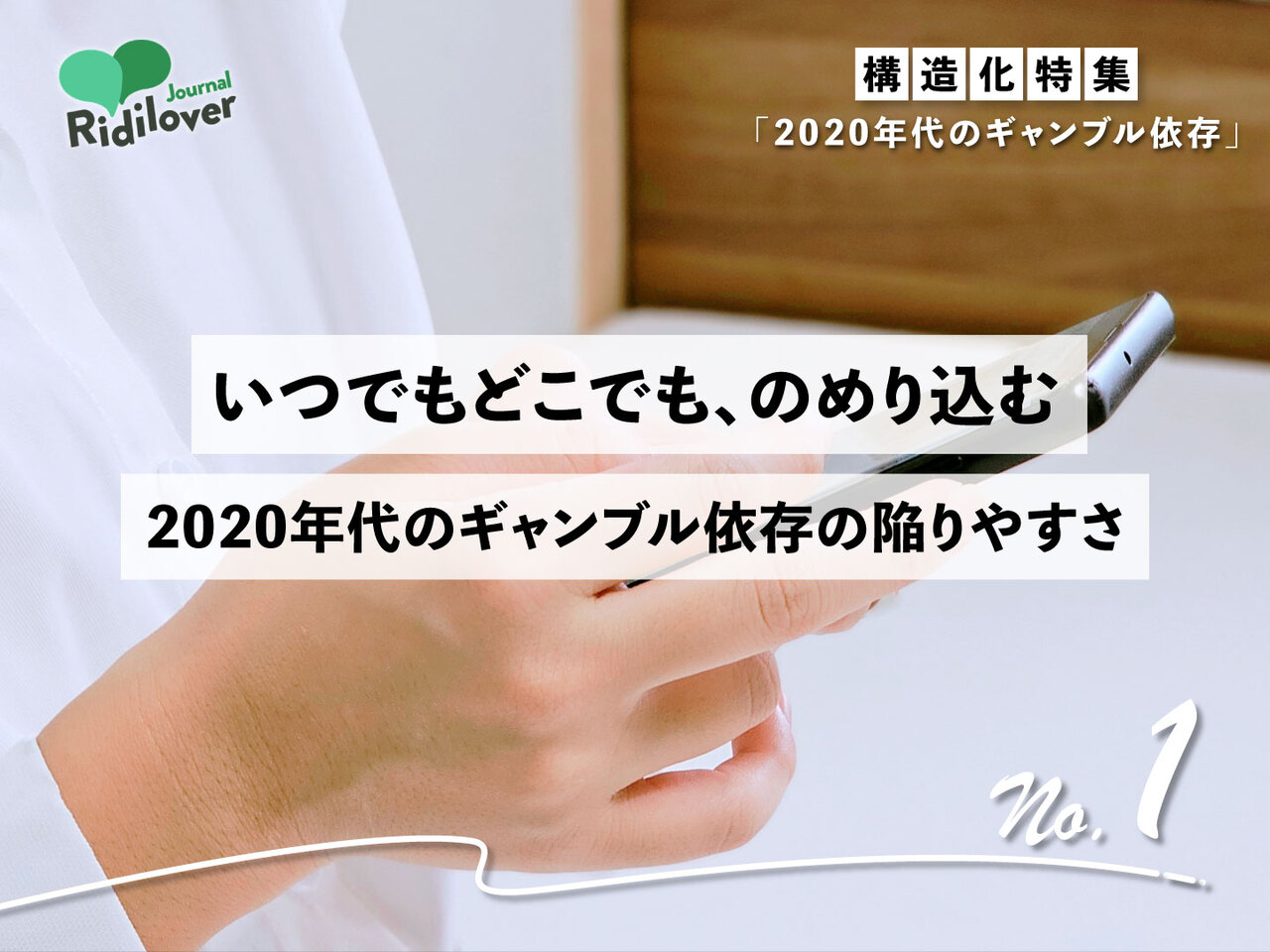



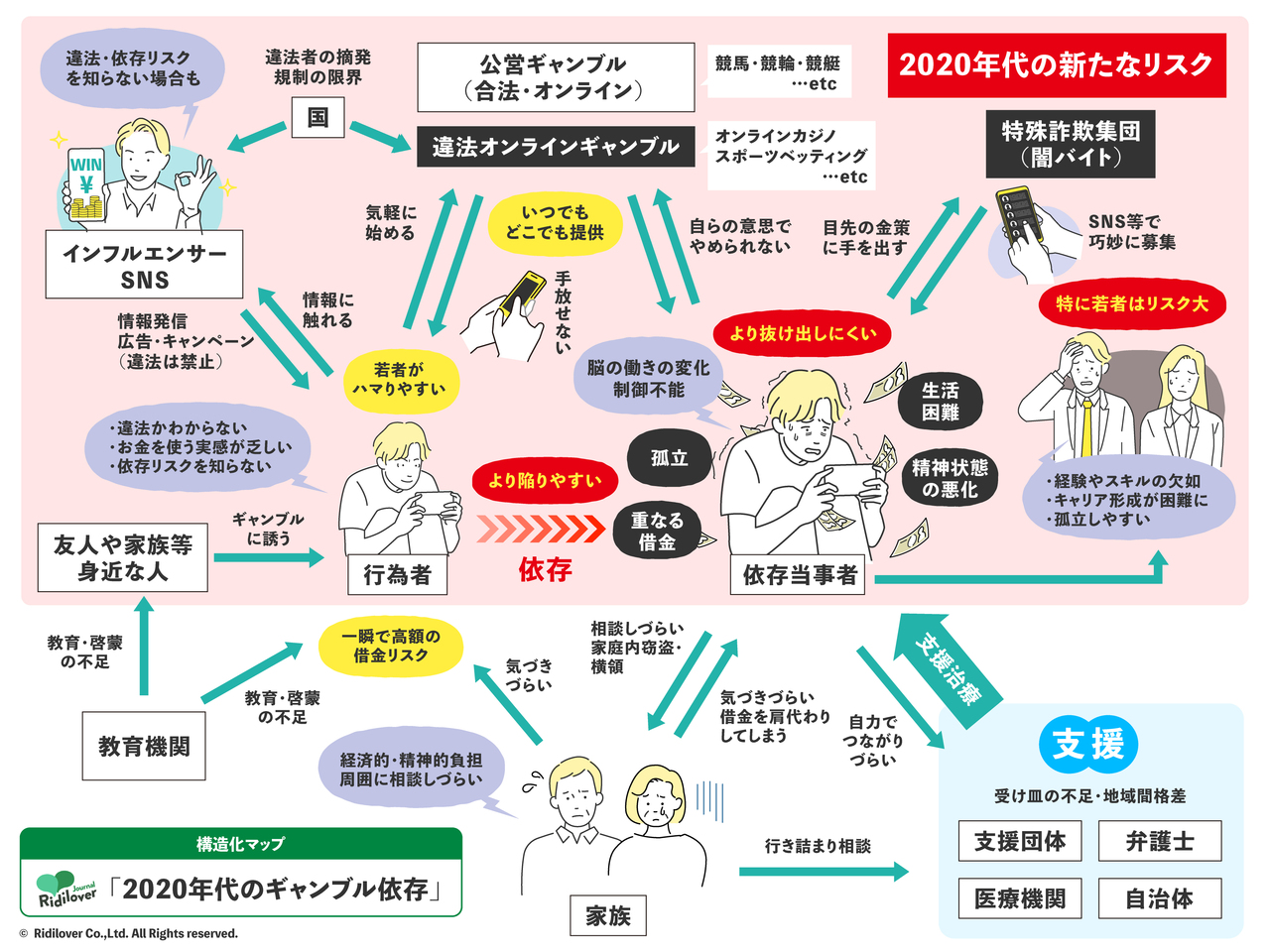






こんにちは。リディラバジャーナルです。「社会貢献したい。だけど具体的に何をしたら良いかわからない」「社会課題へ関心を持ち続けたいけど、SNSで言い争っている人たちがいたから、見なかったことにした」そんなモヤモヤを抱える大学生のみなさんへ、持続可能な社会課題との向き合い方のヒントとなる記事をお届けします。
※このページからリディラバジャーナルの記事にアクセスすると、どなたでも3月3日(火)まで無料でお読みいただけます!
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる