公開日: 2022/1/19(水)
人間の活動がウナギを苦しめる――ウナギ問題から持続可能な食を考える(後編)
公開日: 2022/1/19(水)

公開日: 2022/1/19(水)
人間の活動がウナギを苦しめる――ウナギ問題から持続可能な食を考える(後編)
公開日: 2022/1/19(水)
日本人にとって馴染みの深いウナギ。その急激な減少の背景には、気候変動や生息環境の悪化といった環境の問題、ウナギの養殖に用いるシラスウナギの過剰な採捕や密漁といった漁業の問題などが複雑に絡み合っている。
前編に引き続き、ウナギの保全と持続的利用を目指す専門家として2020年よりロンドンで研究を行っている中央大学法学部教授 海部健三さんの視点から、後編では、ウナギをめぐる日本の状況を紐解き、問題の解決が進まない構造的要因を考察する。
※取材は「リディ部〜社会問題を考えるみんなの部活動〜」で行われたライブ勉強会「ウナギ問題から持続可能な食を考える〜問題の背景や全体像とは〜」で行われました。
海部 健三さん(中央大学法学部 教授、Honorary Conservation Fellow, Zoological Society of London、国際自然保護連合(IUCN)種の保存委員会 ウナギ属魚類専門家グループ)
1973年東京都生まれ。一橋大学社会学部を卒業後、社会人生活を経て2011年に東京大学農学生命科学研究科の博士課程を修了。東京大学大学院農学生命科学研究科特任助教、中央大学法学部准教授を経て、2021年4月より現職。専門は保全生態学で、ウナギ属魚類の保全と持続的利用を目指した研究活動を行う。2014年度・2015年度環境省ニホンウナギ保全方策検討委託業務において研究代表者を務める。著書に「結局、ウナギは食べていいのか問題」(岩波書店)、「ウナギの保全生態学」(共立出版)、「わたしのウナギ研究」(さ・え・ら書房)など。
1973年東京都生まれ。一橋大学社会学部を卒業後、社会人生活を経て2011年に東京大学農学生命科学研究科の博士課程を修了。東京大学大学院農学生命科学研究科特任助教、中央大学法学部准教授を経て、2021年4月より現職。専門は保全生態学で、ウナギ属魚類の保全と持続的利用を目指した研究活動を行う。2014年度・2015年度環境省ニホンウナギ保全方策検討委託業務において研究代表者を務める。著書に「結局、ウナギは食べていいのか問題」(岩波書店)、「ウナギの保全生態学」(共立出版)、「わたしのウナギ研究」(さ・え・ら書房)など。

(海部 健三さん)
違法シラスウナギはなぜ問題なのか
無報告、密漁、密輸のシラスウナギが入り混じり、違法な状態がまかり通ること自体が問題だが、問題はそればかりではない。
この状態は、ニホンウナギの資源解析とそれに基づいた適切な消費上限の設定を困難にしてしまうと海部さんは言う。
「資源解析というのは、今ウナギがどれぐらいいて、増えているのか減っているのかをデータに基づいて判断することです。
密漁が横行し、また、各県に報告されたシラスウナギが、実際に獲った量の半分ぐらいしかないとしたら、その漁業データはデータ解析に使えません。データに基づいた漁業管理自体が成立しないということです」
※リディラバジャーナルについてもっと知りたい方はコチラ
イシューから探す





































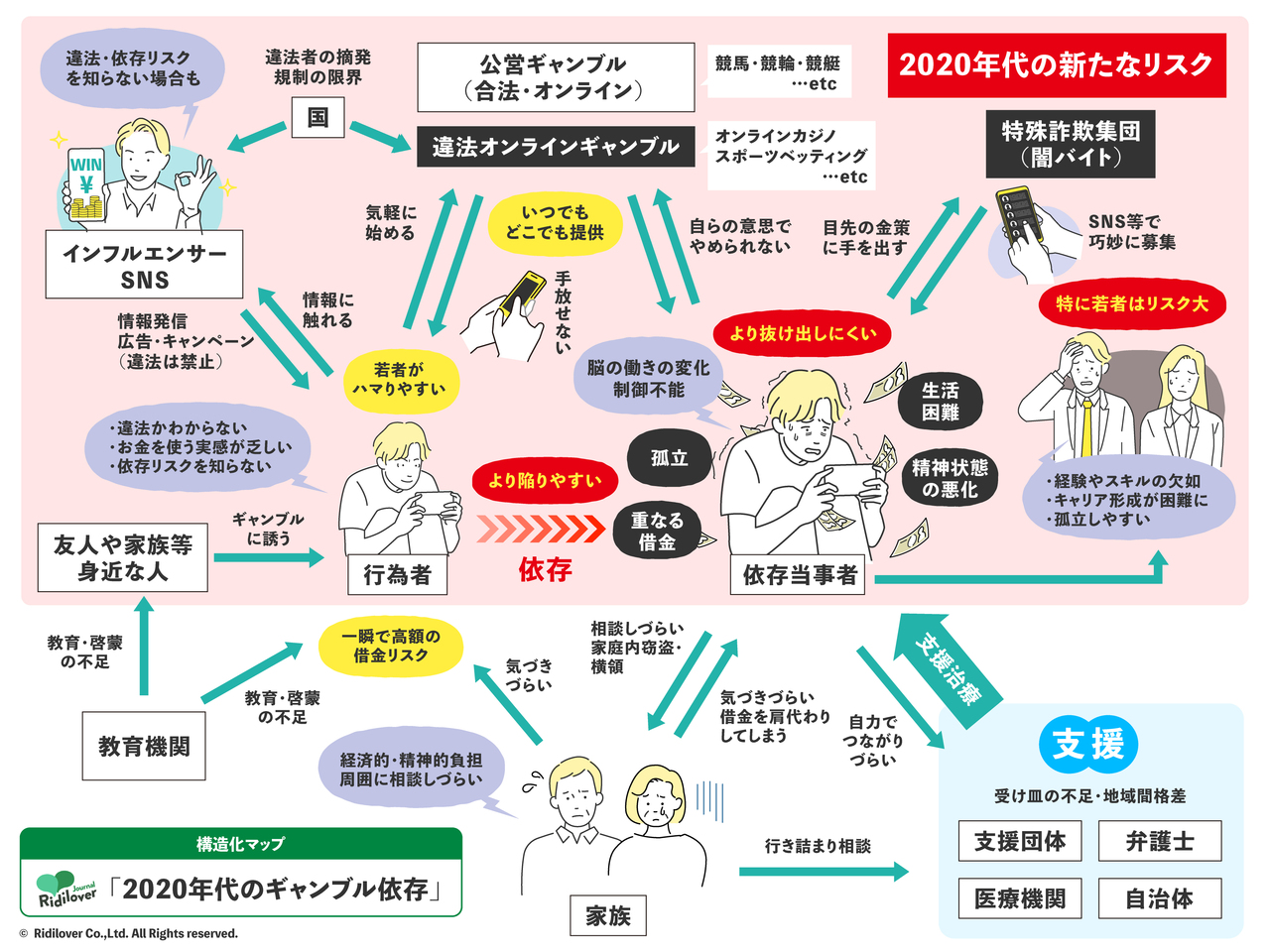






ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる