公開日: 2022/3/10(木)
小さな村の小さな取り組みが国を動かす――チョコレートの裏に潜む児童労働(後編)
公開日: 2022/3/10(木)

公開日: 2022/3/10(木)
小さな村の小さな取り組みが国を動かす――チョコレートの裏に潜む児童労働(後編)
公開日: 2022/3/10(木)
私たちが日々口にするチョコレート、その裏側には児童労働の問題が潜んでいる。
チョコレートの原料であるカカオの生産現場では、児童労働が常態化しており、たくさんの子どもたちが生活のため、家族のために働かざるを得ない状況にある。
今回は、カカオの一大産地であるガーナを中心に、児童労働の問題解決に挑み、子ども・若者の権利を奪う社会課題の解決を目指す「特定非営利活動法人 ACE(エース)」の白木朋子副代表にインタビュー。
前編では、白木さんが児童労働の問題に足を踏み入れるきっかけから、児童労働の現状、そして問題提起から100年以上が経過した今も問題解決が進まない背景を聞いた。
今回の後編では、この複雑な児童労働の問題に対してACEがどのようにアプローチをしたのか、「しあわせへのチョコレートプロジェクト」の取り組みについて聞く。
※取材は「リディ部〜社会問題を考えるみんなの部活動〜」で行われたライブ勉強会「カカオ生産地の児童労働をなくすために 〜『チョコ』から見える巨大な問題構造〜」で行われました。
白木朋子さん(特定非営利活動法人 ACE 副代表)
大学のゼミでインドの児童労働を研究。現地のフィールドワークで児童労働を余儀なくされる子どもたちと出会い、強い衝撃を受ける。
大学在籍中の1997年、代表の岩附ほか学生5人でACEを創業。英国留学、民間の開発援助コンサルティング会社での勤務を経て、2005年4月から2021年11月までACE事務局長を務める。2021年に事務局長を退任し同副代表に就任。
ガーナのカカオ生産地域で子どもの教育やカカオ農家の自立を支援する「スマイル・ガーナ プロジェクト」を、2009年に開始。「児童労働のないチョコレート」の開発・普及や、サプライチェーンの人権に関する企業の支援や連携、国際会議での発信やネットワーク構築等にも従事。2018年からは、ガーナ政府と共同で、「児童労働フリーゾーン」制度の構築にも取り組む。
明治学院大学国際学部卒業。英国ロンドン大学東洋アフリカ大学院国際教養ディプロマ課程、英国サセックス大学・文化環境開発研究所、開発人類学修士課程修了。
「チェンジの扉~児童労働に向き合って気づいたこと」(2018年、集英社)、「子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。」(2015年)、共著「わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。」(2007年)(いずれも合同出版)。ACE創設15周年記念映画「バレンタイン一揆」(2012年公開)には案内役として登場。
大学のゼミでインドの児童労働を研究。現地のフィールドワークで児童労働を余儀なくされる子どもたちと出会い、強い衝撃を受ける。
大学在籍中の1997年、代表の岩附ほか学生5人でACEを創業。英国留学、民間の開発援助コンサルティング会社での勤務を経て、2005年4月から2021年11月までACE事務局長を務める。2021年に事務局長を退任し同副代表に就任。
ガーナのカカオ生産地域で子どもの教育やカカオ農家の自立を支援する「スマイル・ガーナ プロジェクト」を、2009年に開始。「児童労働のないチョコレート」の開発・普及や、サプライチェーンの人権に関する企業の支援や連携、国際会議での発信やネットワーク構築等にも従事。2018年からは、ガーナ政府と共同で、「児童労働フリーゾーン」制度の構築にも取り組む。
明治学院大学国際学部卒業。英国ロンドン大学東洋アフリカ大学院国際教養ディプロマ課程、英国サセックス大学・文化環境開発研究所、開発人類学修士課程修了。
「チェンジの扉~児童労働に向き合って気づいたこと」(2018年、集英社)、「子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。」(2015年)、共著「わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。」(2007年)(いずれも合同出版)。ACE創設15周年記念映画「バレンタイン一揆」(2012年公開)には案内役として登場。
ACEは児童労働にどう立ち向かったか
「しあわせへのチョコレートプロジェクト」の取り組み
ACEでは2009年から、「しあわせへのチョコレートプロジェクト」という取り組みを続けている。この取り組みについて、白木さんは次のように語る。
「児童労働の問題は根深く、色々なところに原因があるのですが、私たちはまず現場で犠牲を払っている子どもに、直接的な改善をもたらそうと思いました。
※リディラバジャーナルについてもっと知りたい方はコチラ
イシューから探す





































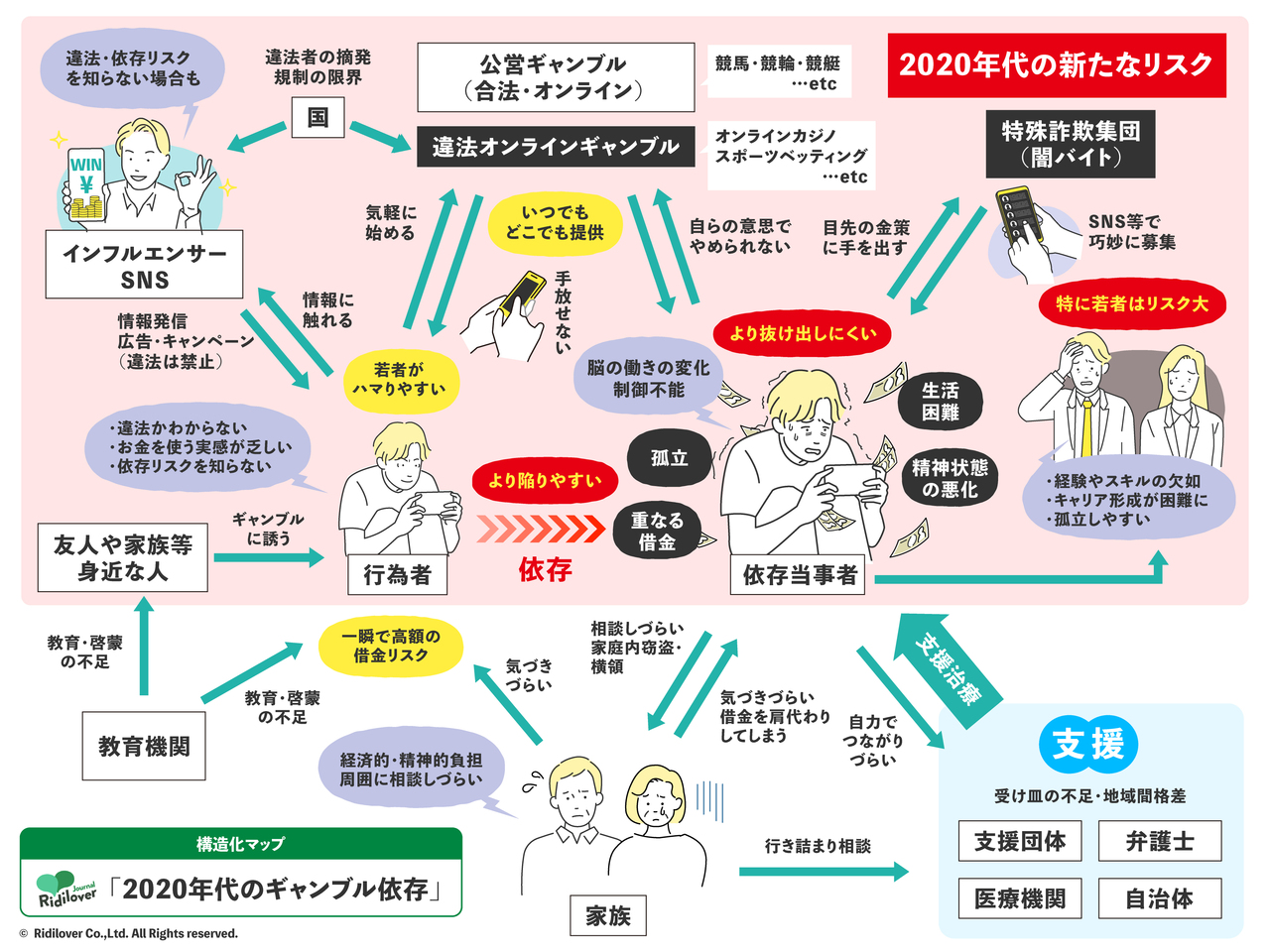






ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。
続きをみる